
知財戦略を作るのは、将来を思い描くことだよね。
将来を描くのは難しいな~。



そうだね。いきなり将来を描くのは難しいから、
まずは、自身の強みと弱みを把握することだよ。



強みと弱みか。
何でそれが必要なの?



それはね、強みを伸ばし、弱みを補うことが、戦略に繋がるからだよ。
今回は、その方法を詳しく見ていこう!
「うちの会社、技術力はあるはずなのに、なぜか競合に差をつけられている気がする…」
「知財戦略って重要だとは聞くけど、何から手をつければいいのか分からない…」
「自社の本当の強みって、一体何なんだろう?」
もしあなたが、このような疑問や課題を感じているなら、この記事はきっとお役に立てるはずです。
企業の成長に欠かせない「知的財産戦略」。
しかし、その戦略を描くためには、まず「己を知る」こと、つまり自社の現在地を正確に把握することが不可欠です。
この記事では、知財戦略立案の基礎となる自社の「強み」と「弱み」を明らかにするための具体的な方法として、競合他社との比較分析をご紹介します。
難しく考える必要はありません。
4つのシンプルな視点から自社とライバルを見つめ直すことで、これまで気づかなかった「武器」や、克服すべき「弱点」が見えてきます。
この記事を読み終える頃には、あなたはきっと、自社の価値を再発見し、勝てる知財戦略を描くための確かな一歩を踏み出せるはずです。
✓ なぜ知財戦略に「強み・弱み」の把握が不可欠なのか
✓競合比較で自社の「強み・弱み」を洗い出す4つの視点
✓各視点で、具体的に何を、どうやって比較すれば良いのか
視点1:商品・サービス比較 ~お客様に選ばれる「理由」を探る~
まずは、あなたの会社が提供している商品やサービスを、競合のものと比べてみましょう。
「お客様はなぜ、自社の商品(サービス)を選んでくれるのか?」その理由を探るつもりで比較するのがポイントです。
何を比べる?
- 機能面: 他社にはない独自の機能や特徴は?逆に、他社にあって自社にない機能は?(本当に必要な機能か?)
- 品質面: 品質レベルは?(顧客満足度、不良率など)安定供給はできていますか?
- 価格: 価格設定は競合と比べて高い?安い?その価格に見合う価値を提供できていますか?
- デザイン: 見た目や使いやすさはどうでしょうか?ブランドイメージに合っていますか?
- 顧客層: どんなお客様がターゲット?競合とのターゲット層の違いは?
どうやって調べる?
- 自社・競合のウェブサイト、カタログ、パンフレット
- 顧客アンケート、レビューサイト(Amazon、楽天、価格.comなど)、SNSでの評判
- 展示会やセミナーでの情報収集、競合製品の購入・試用
- 営業担当者や顧客サポート担当者からのヒアリング
何が見えてくる?(チェック!)
・ 他社には真似できない、自社だけの「売り」は何ですか?
・ お客様が不満に感じている点や、改善を望んでいる点はありますか?
・ 価格競争に巻き込まれず、「価値」で選ばれる理由はありますか?
この比較から、自社商品・サービスの市場における立ち位置、差別化ポイント、そして改善すべき課題(弱み)が明確になります。
視点2:知的財産比較 ~見えない「資産」で優位性を築く~
次に、目には見えにくいけれど、企業の競争力を大きく左右する「知的財産」の面から比較してみましょう。
特許やブランド(商標)、独自ノウハウは、事業を守り、成長させるための強力な武器になります。
何を比べる?
- 特許: どんな技術に関する特許を持っていますか?その特許は事業の核となる技術を守っていますか?競合他社の特許出願状況は?(将来の脅威は?)
- 商標: 自社のブランド(社名、商品名、ロゴ)は商標登録されていますか?ブランドはお客様にどう認識されていますか?(ブランド力、認知度)
- ノウハウ: 特許にはなっていないけれど、社内に蓄積された独自の技術、製造方法、顧客データなどはありますか?(他社が真似できない「秘伝のタレ」)
どうやって調べる?
- 特許: 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で自社名・競合名、関連技術キーワードで検索
- 商標: J-PlatPatや商標検索サービスで調査
- ノウハウ: 社内の技術者、開発者、製造担当者へのヒアリング、技術文書の棚卸し、退職者からの情報漏洩リスクの確認
何が見えてくる?(チェック!)
・ 自社の「強み」である技術は、特許でしっかり守られていますか?
・ ブランド名やロゴは、安心して使い続けられますか?(他社の権利を侵害していませんか?)
・ 社内の貴重なノウハウは、きちんと管理・継承されていますか?
・ 競合が力を入れている技術分野(特許出願動向から)は何ですか?
知財の比較分析は、自社の技術的優位性やブランド価値を客観的に評価し、将来のリスクに備える上で非常に重要です。
視点3:事業内容比較 ~ビジネスの「骨格」を比べる~
ここでは、会社全体のビジネスの仕組みや規模感を比較します。どのようなビジネスモデルで収益を上げ、市場でどれくらいの存在感があるのかを見ていきましょう。
何を比べる?
- ビジネスモデル: 収益を上げる仕組みは?(例: 製品販売、サブスクリプション、ライセンス供与など)競合との違いは?
- 事業規模: 売上高、利益、従業員数などを比較。成長率はどうですか?
- 市場シェア: 参入している市場でのシェアはどのくらい?
- 顧客基盤: どのような顧客をどれくらい抱えていますか?(リピート率、顧客単価など)
- 販売チャネル・パートナー: どのような経路で販売していますか?(直販、代理店、ECなど)協力会社との関係は?
どうやって調べる?
- 自社・競合のウェブサイト(会社概要、IR情報 ※上場企業の場合)
- 業界レポート、市場調査データ
- ニュース記事、プレスリリース
- 信用調査会社の情報(有料の場合あり)
何が見えてくる?(チェック!)
・ 自社のビジネスモデルは、競合と比べて収益性や持続可能性で優れていますか?
・ 事業規模や市場シェアから見て、自社の業界でのポジションは?
・ 安定した収益を支える優良顧客や、強力な販売パートナーはいますか?
事業全体の比較により、自社の経営基盤の安定性や成長ポテンシャル、そして事業構造上の課題が見えてきます。
視点4:経営理念の比較:企業文化や価値観の違いから戦略の方向性を定める
最後に、少し抽象的に感じるかもしれませんが、企業の根幹をなす「経営理念」や「企業文化」を比較してみましょう。どのような価値観を大切にし、どこへ向かおうとしているのかを知ることは、長期的な戦略を考える上で欠かせません。
何を比べる?
- 経営理念・ビジョン: 会社が目指す姿、社会に提供したい価値は?競合との違いは?
- 企業文化・風土: 社内の雰囲気、意思決定のスタイル、大切にされている価値観は?(例: 挑戦を奨励する文化、チームワーク重視など)
- 人材: どのような人材が集まり、活躍していますか?(社員のスキル、モチベーションなど)
どうやって調べる?
- 自社・競合のウェブサイト(経営理念、トップメッセージ、会社沿革、採用情報など)
- 統合報告書、CSRレポート
- メディアでの経営者の発言、インタビュー記事
- (自社の場合)社員へのヒアリング、社内報
何が見えてくる?(チェック!)
・ 経営理念は、日々の事業活動や社員の行動に具体的に反映されていますか?
・ 自社ならではの企業文化は、競争優位性の源泉になっていますか?
・ 理念に共感し、事業を推進してくれる人材が集まっていますか?
経営理念や企業文化は、社員の求心力を高め、一貫した戦略実行を支える土台となります。
自社らしさ(DNA)を再確認しましょう。
まとめ
さて、ここまで4つの視点から自社と競合を比較する方法を見てきました。
- 商品・サービス比較 → 市場での競争力、顧客価値
- 知的財産比較 → 技術的優位性、ブランド力、見えない資産
- 事業内容比較 → ビジネスモデル、経営基盤、市場ポジション
- 経営理念比較 → 企業文化、組織力、進むべき方向性
大切なのは、これらの分析結果をバラバラに捉えるのではなく、点と点を繋いで線として、総合的に自社の「強み」と「弱み」を特定することです。
- 例えば、「商品力(視点1)は弱いが、それをカバーできる強力な特許(視点2)がある」かもしれません。
- 「独自の技術(視点2)があるのに、それを活かすビジネスモデル(視点3)になっていない」という課題が見えるかもしれません。
- 「素晴らしい経営理念(視点4)があるのに、商品(視点1)や事業(視点3)に反映されていない」というギャップに気づくかもしれません。
このように、複数の視点からの分析結果を掛け合わせることで、より本質的な自社の姿が見えてきます。
さあ、羅針盤は手に入れました!
今回明らかになった自社の「強み」と「弱み」。これは、あなたの会社が未来へ進むための重要な道しるべです。
次のステップでは、この内部環境の分析結果(強み・弱み)と、市場や競合の動向といった外部環境の分析(機会・脅威)を組み合わせて、「SWOT分析」を行います。これにより、自社が取るべき具体的な戦略の方向性が見えてきます。
次回【Step3-2 事業の方向性を描く】では、この「SWOT分析」と、さらに戦略を具体化する「クロスSWOT分析」について詳しく解説します。
ぜひ、今回の分析結果を手に、次のステップへ進んでみてください!
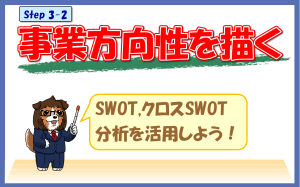
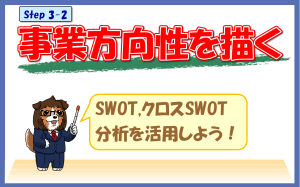
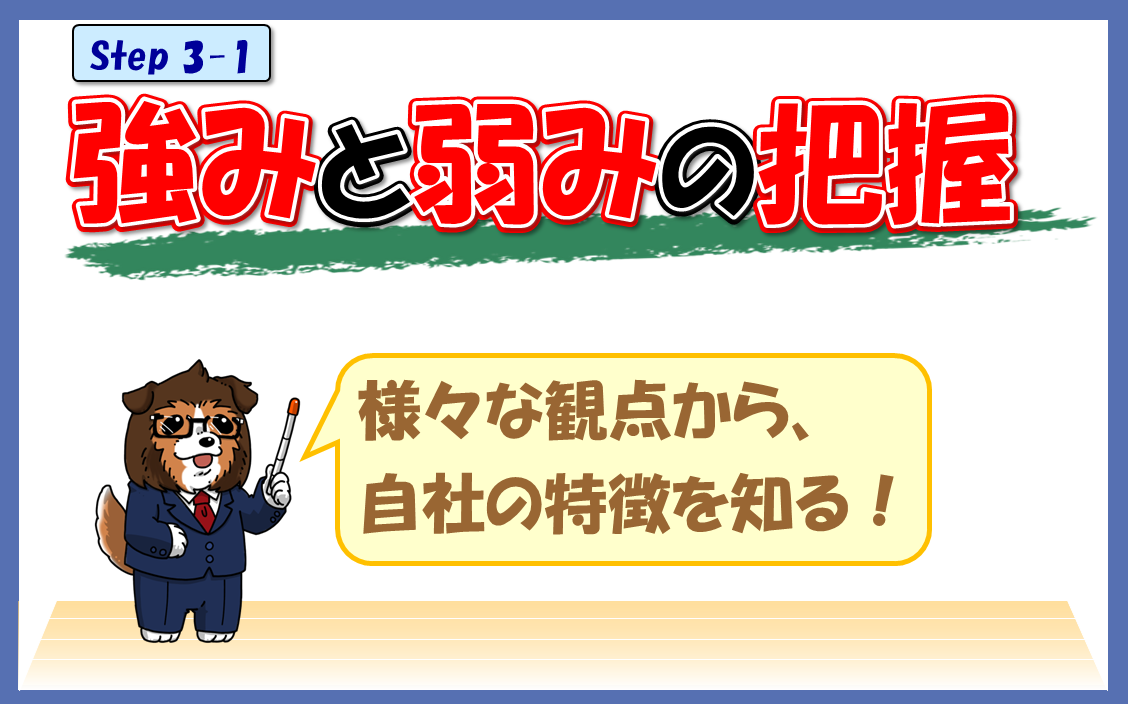

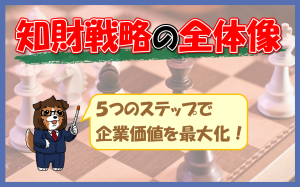
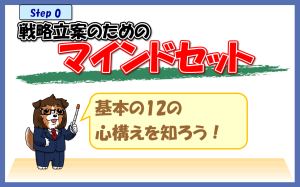
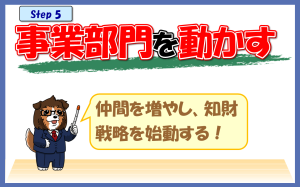
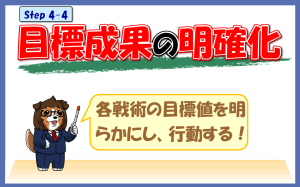
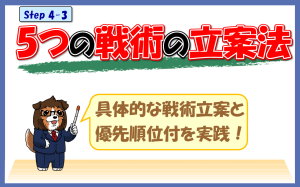
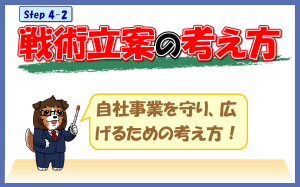
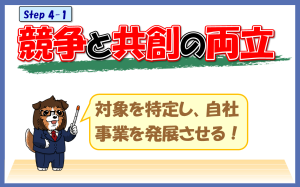
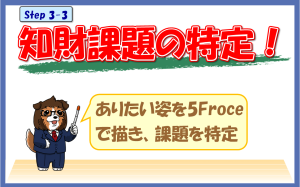
コメント