
ありたい姿って、どうやって定めるのがいいのかな。



そうだね。知財部門だけで決めるって訳にもいかないからね。
やはり、事業部門との連携が必要だよ。



そっか。そうすると、ありたい姿だけではなく、
実際の課題への取組みも連携が必要だね。



そのとおり。
今回は、ありたい姿と、課題の特定について、詳しく説明して行くよ。
「前回までの分析で、いくつか魅力的な未来(ありたい姿)の候補が見えてきたぞ!」
「でも、どの未来を目指すのが本当にベストなんだろう?」
「知財部だけで突っ走って、現場と温度差が生まれないかな…?」
前回のSWOT/クロスSWOT分析を経て、そんな期待と同時に、新たな疑問や不安を感じている知財担当者、そして経営者の皆さまもいらっしゃるのではないでしょうか。
複数の「ありたい姿」候補から、会社全体が納得し、実現に向けて一丸となれる「真のありたい姿」を一つに定め、そこへ至るための具体的な「課題」を特定する――。
これこそが、特許戦略・知財戦略立案の【Step3:将来を描く】における、まさに「要諦」と言える最終工程です。
「じゃあ、どうやって一つに絞り、課題を見つけるんだ?」
そのカギを握るのが、①現場のリアルを知る「事業部門との連携」と、②業界構造の変化を捉える「5Force分析による現状との比較」です。
今回の記事では、この2つのアプローチを用いて、机上の空論ではない、血の通った「ありたい姿」を特定します。
そしてそれを阻む「事業上の課題」と、その解決に不可欠な「知財上の課題」を明確にする、実践的なステップを解説します。
✓ 部門間の壁を越え、共感と納得感のある「ありたい姿」を定めることができる。
✓ 5Force分析で、現状と未来のギャップ=真の課題を客観的に特定できる。
✓ 事業課題と連動した、的確な「知財課題」を見つけ出し、次なる戦略立案への道筋をつけられる。
さあ、未来を掴むための最終工程へ進みましょう!
1. 単なる報告じゃない!事業部門と「共創」するヒアリング
SWOT/クロスSWOT分析の結果、知財部の視点からいくつかの「ありたい姿」候補が見えてきたはずです。
しかし、それをそのまま戦略として進めるのは危険です。
なぜなら、事業の最前線にいる事業部門の視点が欠けているからです。
なぜ事業部ヒアリングが不可欠なのか?
・現場のリアルな情報:
顧客の声、市場の肌感覚、競合の生々しい動きなど、データだけでは見えない貴重な情報が得られます。
・実現可能性の検証:
描いた「ありたい姿」が、現場のリソースやケイパビリティで本当に実現可能か、現実的なフィードバックが得られます。
・「腹落ち感」と実行へのコミットメント:
一方的に伝えられた戦略よりも、共に考え、創り上げた「ありたい姿」の方が、実行段階での当事者意識と協力度合いが格段に高まります。
ヒアリングを「共創の場」にするためのコツ
1. 十分な事前準備:
SWOT/クロスSWOT分析の結果と、「ありたい姿」候補を、事業部の言葉で分かりやすく資料にまとめ、事前共有します。
2. 仮説を提示し、意見を求める:
「我々はこう考えたのですが、皆さんの視点から見てどうですか?」「この『ありたい姿』の実現には、どんな課題がありそうですか?」と、具体的な問いを投げかけます。
3. 傾聴と対話を重視:
知財部の考えを押し付けるのではなく、事業部の意見や懸念に真摯に耳を傾け、双方向の対話を心がけます。
なぜそう考えるのか?背景にある事実は何か?を深掘りしましょう。
4. 事業目標への貢献視点:
「この『ありたい姿』は、皆さんの事業目標達成にどう貢献できるか?」という視点で対話し、共通のゴールを見据えます。
2. 「ありたい姿」を磨き上げる!進むべき道を選ぶプロセス
事業部とのヒアリングで得られた意見やインサイトを踏まえ、いよいよ複数の「ありたい姿」候補の中から、会社として目指すべき一つの方向性を特定します。
これは単なる「選択」ではなく、議論を通じて「磨き上げる」プロセスです。
・全社戦略との整合性:
会社の経営方針や長期ビジョンとベクトルが合っているか?
・事業としての魅力・成長性:
十分な市場規模や成長が見込めるか? 収益性はどうか?
・自社の強みの活用と実現可能性:
自社のコアコンピタンスやリソース(ヒト・モノ・カネ・チザイ)で実現可能か? 強みを活かせるか?
・競合に対する優位性:
競合他社との差別化を図り、持続的な競争優位を築けるか?(知財による参入障壁も考慮)
・事業部門の納得感・コミットメント:
関係部署が「自分たちの目指す未来だ」と共感し、主体的に関与できるか?
これらの基準に基づき、議論を重ね、関係者が「これだ!」と腹落ちできる「ありたい姿」を一つに定めましょう。
3. 5Force分析で「未来へのギャップ」をあぶり出す
目指すべき「ありたい姿」が定まりました。
しかし、現状からそこへ到達するには、どのような「壁」があるのでしょうか?
そのギャップを客観的に明らかにするのが「5Force(ファイブフォース)分析」です。
5Force分析とは?
マイケル・ポーターが提唱した、業界の収益性を決める5つの競争要因(脅威)を分析するフレームワークです。
1. 新規参入の脅威:
新しい競合が現れる可能性は?(技術的障壁、特許網、ブランド力、規模の経済などが影響)
2. 既存企業間の競争:
業界内の競争はどれくらい激しいか?(競合の数、製品差別化、競合の特許戦略などが影響)
3. 代替品の脅威:
自社製品・サービスに取って代わるものは?(代替品のコスト、性能、関連技術の特許動向などが影響)
4. サプライヤー(売り手)の交渉力:
部品や原材料の供給元の力が強いか?(サプライヤーの寡占度、独自技術・特許の有無などが影響)
5. バイヤー(買い手)の交渉力:
顧客の力が強いか?(顧客の寡占度、製品の差別化度、**顧客が持つ代替選択肢(技術・特許)**などが影響)
ここがポイント! 「現状」と「ありたい姿」の比較分析
5Force分析の真価は、「現状」と「特定した『ありたい姿』が実現した未来」の2つの時点について分析し、比較することにあります。
[ここに5Force分析の比較表イメージを挿入(現状 vs ありたい姿)]
例えば…
- 現状分析: 「サプライヤーの交渉力」が【高い】(特定のサプライヤーの独自技術に依存しているため)。
- ありたい姿分析: 「サプライヤーの交渉力」を【低い】状態にしたい(自社で代替技術を開発・導入し、選択肢を増やす)。
- 見えてくるギャップ: サプライヤー依存から脱却し、交渉力を高める必要がある。⇒ これが「課題」の種になります。
このように比較することで、「ありたい姿」を実現するために、どの競争要因を、どう変えていく必要があるのかが具体的に見えてきます。
分析の際は、各Forceについて知財的な側面(特許による障壁、競合の知財戦略など)も忘れずに評価しましょう。
4. 核心!「事業課題」と「知財課題」を特定する
5Forceの比較分析で見えてきた「ギャップ」。
これを、具体的な「事業上の課題」へと落とし込みます。
そして、ここからが知財戦略の腕の見せ所です。
特定された「事業課題」に対し、それを解決・支援するために取り組むべき「知財上の課題」は何か?
この事業と知財の連動を明確にすることが、戦略の実効性を高めるカギとなります。
以下に、5Forceのギャップから事業課題、そして関連する知財課題へと繋がる考え方の例を示します。
【5Forceギャップ→事業課題→知財課題の連携例】
| 5Force ギャップ(例) | 事業課題(例) | 関連する知財課題(例) |
| 新規参入の脅威が高い | 参入障壁の構築 | ・コア技術・周辺技術の特許網構築 ・模倣困難なノウハウの営業秘密管理 |
| 既存競合との差別化が弱い | 技術的優位性の確立 製品・サービスの独自性向上 | ・競合特許を回避する開発戦略 (FTO調査・設計変更) ・自社独自技術の権利保護 (特許、意匠など) ・必要に応じたライセンス戦略 (導入・クロス) |
| サプライヤーへの依存度が高い | 代替技術の確保 コスト削減・供給安定化 | ・代替技術分野の特許調査 (ランドスケープ) ・自社開発技術の権利化 ・有望技術のライセンス導入・共同開発 |
| ブランド力が弱く、顧客交渉力が低い | ブランド価値向上 顧客ロイヤリティ向上 | ・ネーミング・ロゴ等の戦略的商標出願 ・製品デザインの意匠権保護 ・模倣品・権利侵害への対策強化 |
このように、事業課題と知財課題は常に連動しています。
事業課題の達成に向けて、知財をどう活用し、どんなリスクに備えるべきか?
これを具体的に洗い出すことが、効果的な知財戦略の基盤となります。
5. まとめ:羅針盤は定まった!課題を胸に、次なる行動へ
お疲れ様でした!
これで、特許戦略・知財戦略立案の【Step3:将来を描く】は完了です。
今回のステップを通じて、あなたの会社は、
- 事業部門も巻き込んだ、納得感のある「ありたい姿」
- 5Force分析に基づいた、現状との客観的なギャップ
- そのギャップを埋めるための具体的な「事業課題」と、それを支える「知財課題」
という、未来へ進むための確かな羅針盤と、乗り越えるべき課題リストを手に入れたはずです。
知財は、もはや事業戦略と切り離して考えられるものではありません。
「ありたい姿」の実現に向けて、事業と知財が両輪となって進んでいく。
そのための重要な道筋が見えたのではないでしょうか。
次回:【Step4:行動を決める】へ
羅針盤と課題リストが手に入ったら、次はいよいよ「具体的な行動」を決める番です!
次回【Step4:行動を決める】では、今回特定した「知財課題」を解決し、「ありたい姿」を実現するために、具体的に「何を」「いつまでに」「誰が」行うのかというアクションプランに落とし込みます。
そして、その進捗を測るKPI(重要業績評価指標)を設定する方法について詳しく解説します。
特定した課題を解決し、描いた未来を実現するために。
ぜひ今回の成果を手に、次のステップへ進んでください!
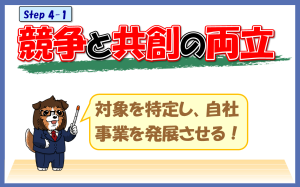
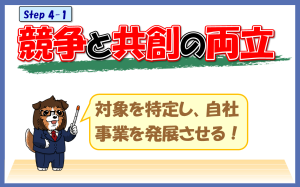
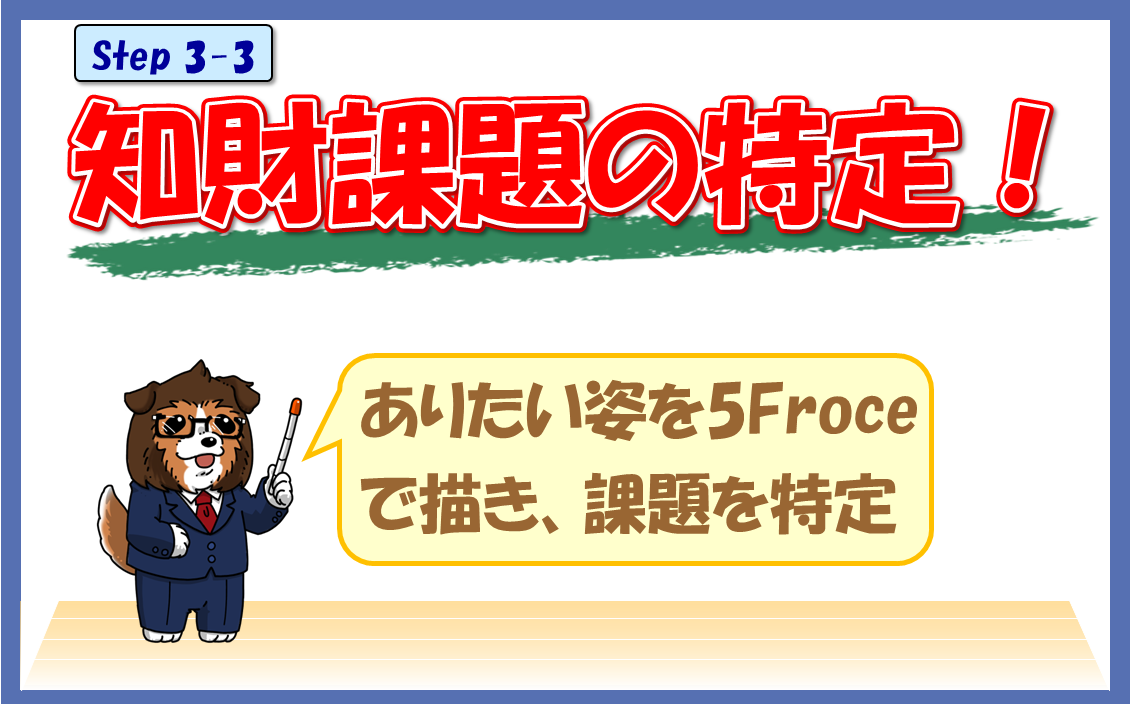

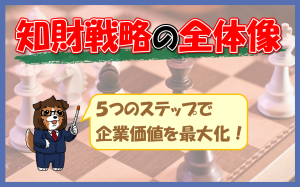
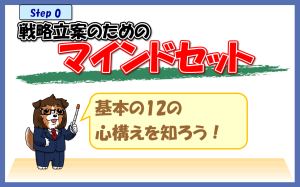
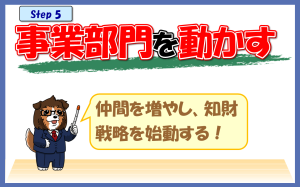
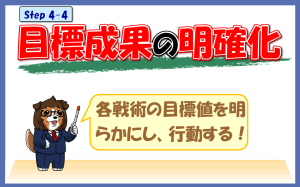
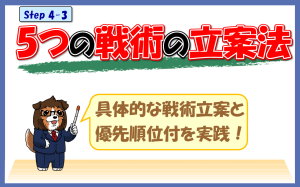
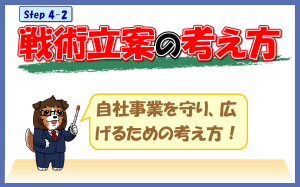
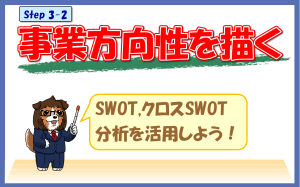
コメント