
将来の事業のありたい姿を思い描いた後は、それを実現させるための、具体的な戦術が必要だね。



そのとおり。
そのためには、戦術を立てるための考え方を知っておく必要があるよ。



考え方かぁ。
確かに、基礎的なことを知らないと、戦術も立てにくいからね。



うん。
今回は、戦術立案の考え方について解説していくよ。
前回の記事では、あなたの事業を取り巻く「競争相手」と「共創相手」が見えてきましたね。
戦うべき相手、組むべき相手が明確になりました。
未来へ進むための地図と登場人物は揃ったのです。
さあ、ここからは【Step4:行動を決める】の第2弾、いよいよ「どんな作戦で臨むか?」です。
つまり、皆さんが思い描いた「ありたい姿」を実現するための、具体的な「知財戦術」をどう組み立てるか、その核心に迫ります。
しかし、焦りは禁物です。
ただやみくもに戦術を考えても効果は薄いでしょう。
大切なのは、特定した「相手」を常に意識すること、そして、「ありたい姿」実現に向けて知財をどう使うか、その「考え方の軸」を持つことです。
今回の記事では、その戦略的な「思考の軸」を皆さんにインストールします。
この記事を読めば、状況に応じた知財戦術を組み立てる基礎が身につきます。
✓「ありたい姿」実現のための知財活用の根源的目的:「お客様に選ばれる」理由作り
✓「攻め」「守り」「協調」という3つの基本的な思考の軸
✓ 戦術実行に伴うリスク管理:「防御」の考え方
✓ 市場を動かす高度な戦術「オープン・クローズ戦略」の視点
思考の軸①:「ありたい姿」実現へ! 知財活用の目的=「お客様に選ばれる」理由を作ること
まず、最も大切な問いから始めましょう。
そもそも、なぜ知財を活用するのでしょうか?
それは、皆さんが思い描いた「ありたい姿」を実現するためです。
では、「ありたい姿」を実現するために、何が必要でしょうか。
それは、「お客様に、他社ではなく『自社の商品・サービスを選んでもらい続ける』こと」ではないでしょうか。
私は、これが知財活用の根源的な目的だと考えます。
お客様が自社を選んでくれる、その「選ばれる理由」は様々です。
独自技術が生み出す優れた機能。心惹かれるデザイン。信頼のブランドなど。
知的財産は、これらの「選ばれる理由」そのものであり、それを支える基盤となります。
そのためには、特許権などの「独占排他権」が重要になります。
この権利は、他社に「選ばれる理由」を安易に真似されないようにします。
自社だけの強みとして守ることで、お客様が自社を選び続けてくれる状況を作り出すのです。
つまり「お客様に選ばれ続ける状況を守る」ことにつながります。
今回の戦術で、あなたは「ありたい姿」実現のために、「どのお客様に」「どの競合と比べて」選ばれたいですか?
そのために、知財をどう使いますか?
この目的意識を持つことが、ブレない戦術の第一歩です。
思考の軸②:「攻め」「守り」「協調」~「選ばれる」ためにどう仕掛けるか?~
目的が明確になったら、次は基本的なスタンスです。
「攻め」「守り」「協調」の3つの軸です。
これも「誰に対して」「選ばれるために」そのスタンスを取るかが重要です。
目的と相手に応じて、大きく3つのスタンス(思考)があります。それぞれの特徴を表にまとめました。
- 【守り】の思考:「選ばれる理由」を守り、事業の自由度を確保する
- 【攻め】の思考:積極的に「選ばれる」状況を作り、優位性を築く
- 【協調】の思考:連携により、より「選ばれる」価値を共創する
| スタンス(思考) | 主な目的 | 主な対象 | 主な知財アクション例 |
| 守り | ・選ばれる理由の保護 ・事業自由度の確保 | 競争相手 | ・自社技術/デザインの権利保護 (特許・意匠等) ・クロスライセンスによる係争回避 |
| 攻め | ・競合との差別化 ・市場優位性の確立 ・収益獲得 | 競争相手、市場 | ・独自技術の特許取得による差別化 ・権利行使による模倣品排除 ・ライセンスアウトによる技術普及/収益化 |
| 協調 | ・新たな価値共創 ・リソース補完 ・開発加速 | 共創相手、業界 | ・共同研究開発 (権利帰属の明確化) ・技術ライセンスイン ・標準化活動への参加 |
これらの軸を、目的と相手に応じて戦略的に使い分けましょう。
それが「選ばれる」ための戦術の骨格です。
思考の軸③:「ありたい姿」への道を阻むリスクに備える~防御の思考~
「ありたい姿」へ向かう道は、常に平坦ではありません。
どんなに優れた計画でも、予期せぬリスクは存在します。
特に知的財産の世界では、他社の権利が壁となったり、自社の権利が攻撃されたりすることがあります。
これらから自社を守り、「選ばれ続ける」状況を維持するための「防御」の考え方も重要です。
防御には、大きく分けて2つのアプローチがあります。
- 【予防的防御】:転ばぬ先の杖
- まず、事前にリスクの芽を摘む考え方があります。これが「予防的防御」です。
- 何を警戒?:「競争相手」の特許。自社の「選ばれる」活動を邪魔する可能性のある権利。
- アクション例: 新製品開発前の先行特許調査(FTO調査)で侵害リスクを回避します。邪魔になりそうな「相手」の特許出願には情報提供等で権利化を阻止することも考えます。
- 【臨床的防御】:万が一の時の備え
- 次に、万が一、実際に攻撃(権利侵害の警告など)を受けた場合の対応策も必要です。これを「臨床的防御」と呼びます。
- 誰から?:主に「競争相手」からの権利侵害警告や訴訟。「選ばれる理由」への直接的な攻撃。
- アクション例: 警告を受けた際の交渉戦略準備。相手の権利を無力化するための無効資料調査。訴訟対応体制の構築。専門家との連携が不可欠です。
防御は、自社の「選ばれる理由」を守り、戦術を安定して実行するための土台となります。
高度な戦術思考:「オープン・クローズ戦略」で市場をデザインする
これは「攻め」や「協調」を発展させた、より高度な戦術の考え方です。
自社の持つ技術(知財)を見渡します。「何を守り(クローズ)、何を開放するか(オープン)」。これを戦略的に設計するのです。
目的は、自社が「選ばれる」ための魅力的なプラットフォームやエコシステムを築くことです。
「選ばれる理由」の源泉となるコア技術は守り(クローズ)。仲間(共創相手)を増やすための技術やインターフェースは開放(オープン)します。
それにより、プラットフォーム全体の魅力を高め、結果として自社(のプラットフォーム)が「選ばれる」状況を作り出すのです。
市場全体のルール形成をも見据えた発想です。
まとめ:思考の軸を武器に、自社だけの「選ばれる」戦法を編み出そう!
今回は、「ありたい姿」実現のための具体的な知財戦術を立案するための「思考の軸」を、「お客様に選ばれる」という目的観から解説しました。
- 根源的目的:「ありたい姿」実現のための「お客様に選ばれる」理由作り
- 基本スタンス:「攻め」「守り」「協調」を使い分ける
- リスク管理:「防御」(予防的・臨床的)の視点を忘れない
- 高度な戦術:「オープン・クローズ」で市場をデザインする
これらの思考の軸を組み合わせ、状況や相手に応じて使い分けること。
それにより、あなたの会社が「選ばれる」ための、ユニークで効果的な知財戦術が見えてくるはずです。
思考の準備は整いましたね?
次回:【Step4-3:事業を成功に導く5つの戦法!】へ
さあ、次はこれらの「考え方」に基づいて、より具体的な「戦法パターン」を見ていきましょう!
次回【Step4-3:事業を成功に導く5つの戦法!】では、今回学んだ思考の軸をベースに、実際のビジネスシーンで活用できる代表的な5つの知財戦術パターンを、具体例を交えて詳しく解説します。
今回インストールした「思考の軸」を武器に、ぜひ次のステップへ進んでください!
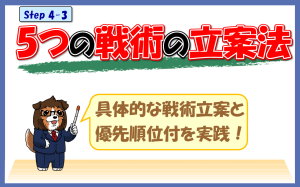
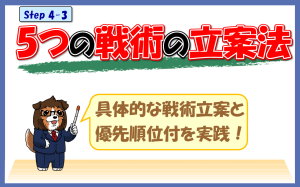
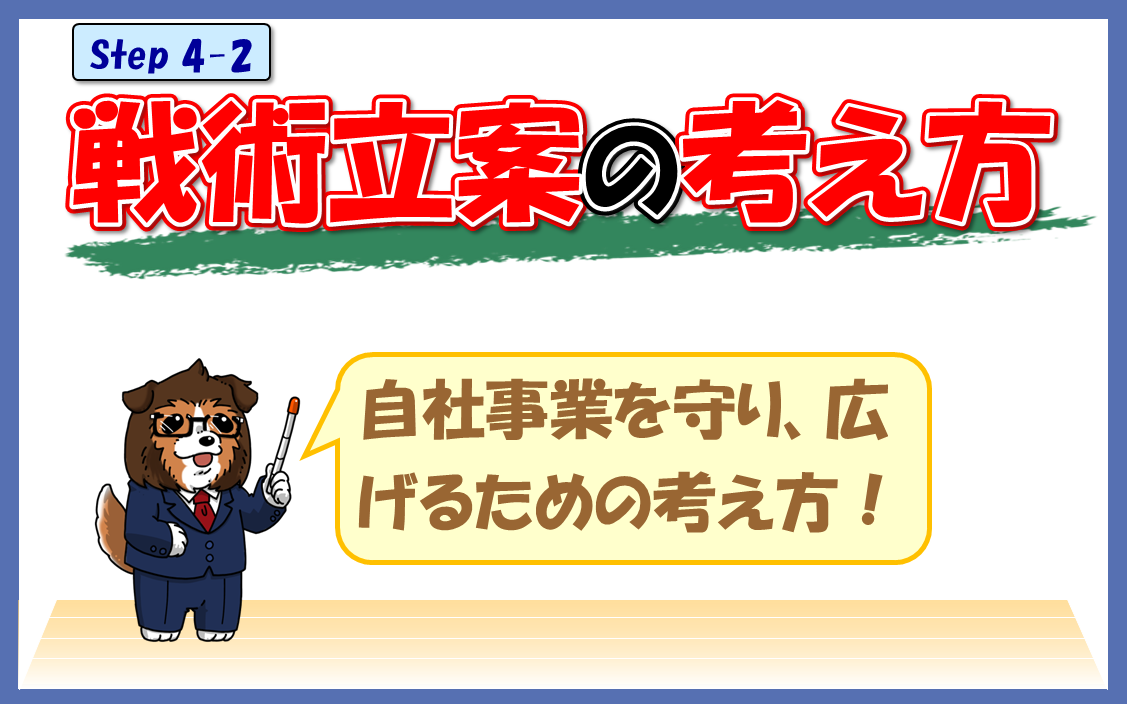

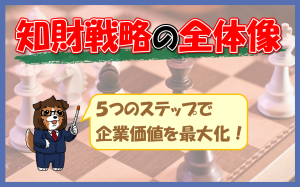
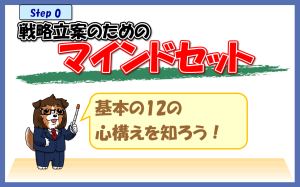
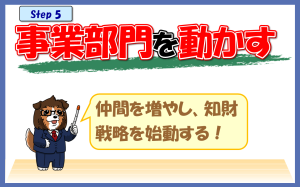
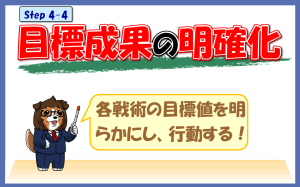
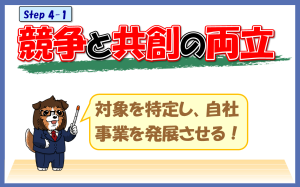
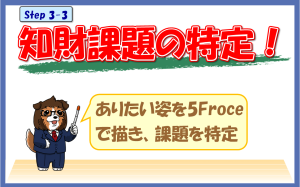
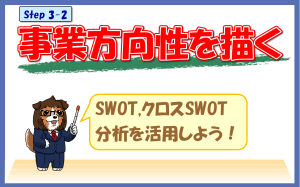
コメント