企業の知財担当者、経営者の皆様、こんにちは。
これまで、知財戦略立案の具体的なステップを解説してきました。
しかし、どんなに優れた手法やフレームワークも、それを扱う「思考のOS」=マインドセットが古いままだと、真の力を発揮できません。
なぜ、ある企業の知財戦略は成功し、ある企業の戦略は空振りに終わるのでしょうか?
その差は、具体的な戦術以前の、物事の捉え方や考え方の「癖」にあるのかもしれません。
「戦略を立てる前に、まず持つべき『心構え』とは何か?」
今回は【Step 0】として、全ての戦略立案の「前提」となるべき重要なマインドセットを13個、厳選してご紹介します。
これらは、古今東西の戦略論や成功企業の事例から導き出された、普遍的な「勝利の法則」とも言える考え方です。
この記事を読めば、あなたの知財戦略立案の思考がアップデートされます。
そして、より本質的で、成功確率の高い戦略を描くための「羅針盤」を手に入れることができるでしょう。
さあ、戦略思考の旅を始めましょう!
✓ 知財戦略立案の「前提」として持つべき13の重要なマインドセット
✓ 各マインドセットが、知財戦略においてどう活きるのか
✓ 戦略思考を深めるためのヒント
【思考のOS ①】全ては「目的」から始まる
1.「目的」(目指す状態=ありたい姿)を設定し、関連者に共有する
戦略は、それ自体が目的ではありません。
必ず**達成したい「目的」**が存在します。
それは、このブログシリーズで繰り返し述べてきた「ありたい姿」です。
まず、「何のためにこの戦略を実行するのか?」という目的を明確に定義しましょう。
そして、その目的(ありたい姿)を関係者全員で共有し、ベクトルを合わせること。
これが全ての始まりです。
知財戦略も、この共有された目的に貢献する手段でなければなりません。
目的がブレると、戦略も必ず迷走します。
【思考のOS ②】「誰と、どう戦うか?」を見極める
目的が定まったら、次は外部環境、特に競争相手との向き合い方を考えます。
2.2者以上の相手を敵として戦わない
経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報・そして知財)は有限です。
複数の競争相手と同時に戦いを挑むのは得策ではありません。
リソースが分散し、どの戦線も中途半端になる危険があります。
戦うならば、標的を一つに絞り、そこにリソースを集中投下する。
これが鉄則です。
知財戦略においても、全ての競合に満遍なく対抗するのではなく、最も脅威となる相手に焦点を当てた対策を考えるべきでしょう。
3.敵の強いところで戦わない (出典:孫子)
「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」(孫子・謀攻篇)。
敵の強みと自社の弱みを分析し、敵の得意とする分野で正面から戦うことを避けるべきです。
古代中国の兵法書『孫子』にもある普遍的な教えです。
相手が圧倒的な強みを持つ分野で、真っ向から勝負を挑むのは避けましょう。
例えば、競合が特定の技術分野で強固な特許網を築いている場合。
その土俵で勝負するのは賢明ではありません。
別の技術領域で優位性を築いたり、相手の特許網を回避する戦略を考えたりする。
これが知財戦略における「敵の強いところで戦わない」実践です。
孫子の兵法は、現代のビジネス戦略にも多くの示唆を与えてくれます。
興味のある方は、ぜひ原典や解説書を手に取ってみてください。
4.弱点、または弱者を攻める
戦いを有利に進める基本は、相手の「弱点」を突くことです。
競合の技術的な弱み、事業展開の隙、あるいは知財ポートフォリオの穴。
そこを見つけ出し、自社の強みをぶつけるのです。
また、市場全体を見渡し、相対的に体力のない「弱者」の領域を攻めるのも有効な戦略です。
知財戦略では、競合の特許の権利範囲の狭さや有効性の疑問点(=弱点)を見つけ出し、そこを突破口とすることも考えられます。
【思考のOS ③】自社の「立ち位置」を知り、戦い方を決める
競争相手を意識しつつ、今度は自社の状況を踏まえた戦い方を考えます。
5.弱者である場合は、まず一点でNo.1になる(ランチェスター戦略)
自社が市場において「弱者」である場合。、広範囲に手を出すのではなく、特定の狭い領域(地域、顧客層、技術分野)に経営資源を集中させましょう。
そして、その一点において圧倒的なNo.1を目指す。
これが有名な「ランチェスター戦略」の弱者の基本戦略です。
知財戦略においても同様です。
スタートアップなどが限られたリソースで戦う場合、**自社のコア技術分野に特許出願を集中させ、まずはその分野での「知財No.1」**を目指すのが有効です。
ランチェスター戦略は、弱者が強者に勝つための実践的なヒントに満ちています。
6.強者である場合は、数の勝負に持ち込む(ランチェスター戦略)
逆に、自社が市場で「強者」である場合、ランチェスター戦略では、物量(シェア、販路、広告宣伝費、そして知財の数)で圧倒し、総合力で勝負することが推奨されます。
弱者が一点突破を狙ってくるのに対し、広範囲な特許網でそれを封じ込め、数の力で押し切る。
これが強者の知財戦略の定石となる場合があります。
ただし、強者であっても油断は禁物です。
7.保有する資源を元に、戦略を決定する(ジェイ・B・バーニー)
戦略は、自社が**「何を持っているか」**に基づいて考えるべきだ。
これがジェイ・B・バーニーなどが提唱するリソースベース戦略の考え方です。
他社が模倣困難な独自の経営資源(技術、ブランド、人材、そして価値ある知的財産)こそが、持続的な競争優位の源泉となります。
あなたの会社の「独自の強みとなる知財」は何ですか?
それを最大限に活かす戦略を考えましょう。
リソースベースの視点は、自社の強みを再認識させてくれます。
8.ポジショニングを決め、「攻め」(参入障壁崩し)と「守り」(障壁強化)を意識する
市場において、自社がどのような**「立ち位置(ポジショニング)」**を目指すのかを明確にしましょう。
そして、そのポジションを守り、あるいは他社のポジションを崩すために、知財をどう使うかを考えます。
自社の市場を守るためには、特許などで「参入障壁」を高くする(守り)。
他社の市場に攻め込むためには、相手の「参入障壁」を乗り越える、あるいは無効化する(攻め)。
この攻守の視点が重要です。
【思考のOS ④】市場を捉え、価値を「独占」する
市場と価値創造について、さらに深く考えてみましょう
9.「独占」こそが大きな利益を生む。それから拡大をする。(ZERO to One)
競争が激しい市場では、利益は限りなくゼロに近づきます。
大きな利益を生むのは、競争がない**「独占」状態**である。
ピーター・ティールは著書『ゼロ・トゥ・ワン』でそう説いています。
まずはニッチな市場で圧倒的な地位(独占)を確立し、そこから徐々に市場を拡大していく。
これが成功への道筋です。
特許権は、まさにこの「独占」を実現するための強力な武器です。
特定の技術や製品で独占的な地位を築き、高収益を確保する。
そのために知財戦略を練るのです。
『ゼロ・トゥ・ワン』は、新しい価値創造を目指す全ての人に示唆を与えます。
10. 人は「情報」を買っている。情報こそ人の行動を支配する力 (出典:梅棹忠夫『情報の文明学』)
私たちはモノやサービスを買っているようで、実はその背景にある「情報」(機能、ブランドイメージ、評判など)に基づいて選択しています。
情報が価値を生み、人の行動を左右するのです。
この考え方は、文化人類学者の梅棹忠夫が『情報の文明学』で論じました。
知財の世界では、「特許情報」がまさに価値ある情報の宝庫です。
競合の技術開発動向、市場の技術トレンドといった重要な情報が詰まっています。
この情報を制する者が、戦略を有利に進めることができるのです。
『情報の文明学』を読むと、現代社会における情報の意味を深く考えさせられます。
【思考のOS ⑤】変化に対応し、未来を描く柔軟性
最後に、戦略を実行し、未来に対応していくためのマインドセットです。
11.外部の優れたものを吸収する
自前主義に固執せず、社外にある優れた技術、アイデア、人材、そして知的財産を積極的に取り入れましょう。
オープンイノベーションの考え方です。
他社からの技術ライセンス導入や共同開発は、自社の弱みを補い、開発を加速させる有効な手段です。
常に外部にアンテナを張り、良いものは柔軟に取り入れる姿勢が、変化の激しい時代には不可欠です。
12.複数のプランを考える(A plan, B plan, C plan)
未来は不確実です。
立てた戦略が常に計画通りに進むとは限りません。
だからこそ、当初の計画(Plan A)がうまくいかなかった場合の代替案(Plan B、Plan C)をあらかじめ考えておくことが重要です。
これをシナリオプランニングと言います。
知財戦略においても、権利化が予定通り進まなかった場合。 競合が想定外の動きを見せた場合など。 複数のシナリオを想定し、対応策を準備しておきましょう。
13.目先に捉われず、少し先を考える
日々の業務に追われると、どうしても目先の課題に目が行きがちです。
しかし、戦略とは本来、未来を見据えて打つ手のことです。
常に「半年後、1年後、3年後、世の中はどうなっているか? 自社はどうなっていたいか?」を問い続けましょう。
目先の利益や効率だけにとらわれず、少し先の未来を予測する。
そして、そこから逆算して今打つべき手を考える。
この未来志向が、持続的な成長の鍵を握ります。
まとめ:マインドセットを更新し、知財戦略を新たな次元へ
今回は、知財戦略を立案する上での「前提」となるべき、13の重要なマインドセットをご紹介しました。
- 目的意識を持つこと。
- 相手を冷静に見極めること。
- 自社の立ち位置と資源を客観的に把握すること。
- 市場と価値の本質を理解すること。
- 変化への柔軟性と未来志向を持つこと。
これらの思考のOSをインストールし、常に意識することで、あなたの知財戦略は、より深く、広く、そして強靭なものへと進化するはずです。
今回触れた「孫子」「ランチェスター戦略」「リソースベース戦略」「ゼロ・トゥ・ワン」「情報の文明学」といった考え方は、それぞれ深遠な内容を含んでいます。
もし、これらの思考法にご興味を持たれたなら、ぜひ関連書籍を手に取り、学びを深めてみてください。
きっと、あなたの戦略思考に新たな光をもたらしてくれるでしょう。
さあ、アップデートされたマインドセットで、あなたの会社の未来を切り拓く、パワフルな知財戦略を描き始めましょう!
【知財戦略立案5ステップシリーズ】
この記事は知財戦略立案シリーズの一部です。
他のステップの記事もぜひご覧ください。
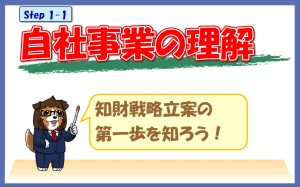
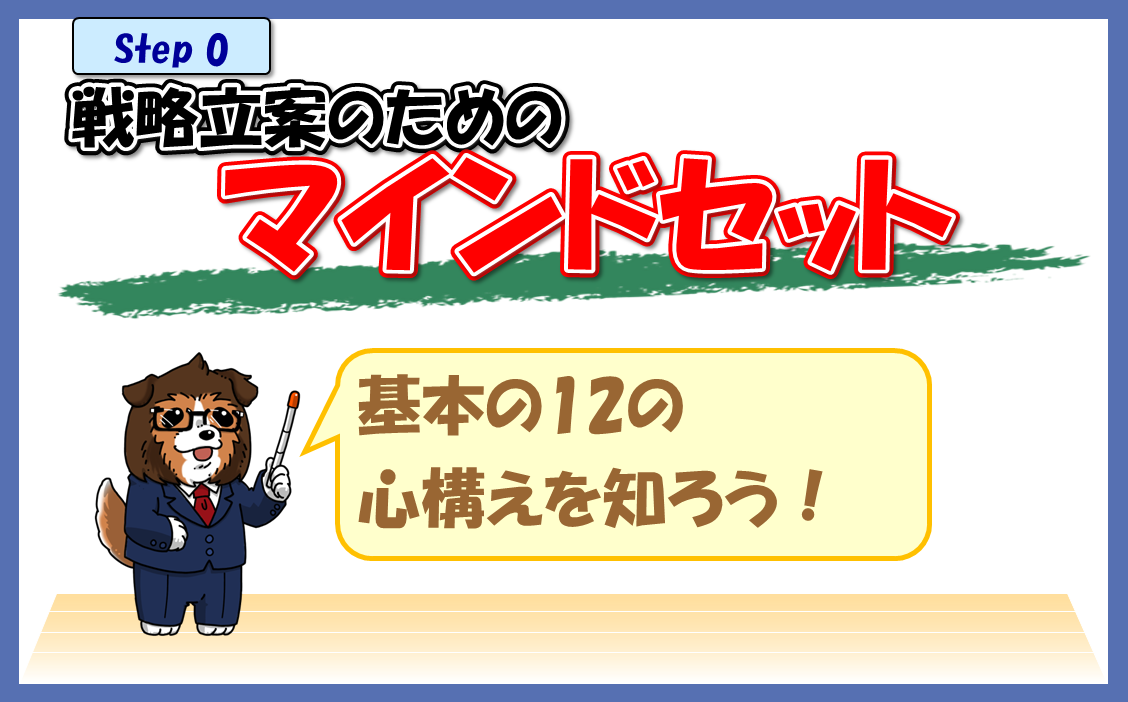

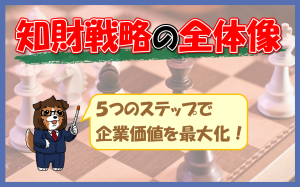
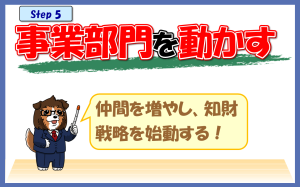
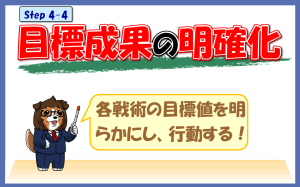
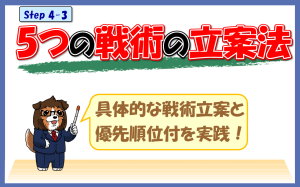
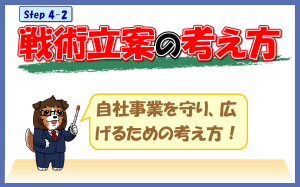
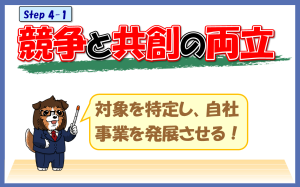
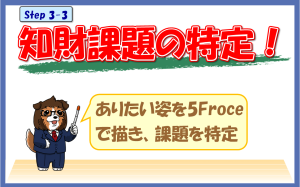
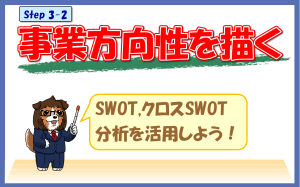
コメント