
知財戦略を作る上で、業界の動向を調べようと思うんだ。
でも、どんな観点で、どのような方法で調べるといいのかな?



特許以外の情報も調べるとは、視野が広くていいよね。
観点や調べ方は色々とあるから、今回はその情報を整理して伝えるよ。
企業の知財担当者、経営者の皆様、こんにちは。
前回【Step2-1】では、PEST分析などを通じて、世の中の大きな流れ(マクロ環境)を捉えましたね。
未来を読む羅針盤を手に入れた気分ではないでしょうか。
さて、大きな地図を確認したら、次は私たちが実際に戦う「業界」という土俵(ミクロ環境)にズームインしましょう。
ここでは、より直接的に自社の事業に影響を与える要因、特に「市場の動向」と「競合の動き」を深く知ることが重要になります。
なぜなら、業界や競合の状況を正確に把握することで、具体的な事業機会や脅威を発見できます。
そして、自社の知財をどう活かせば競争に勝てるか、その戦略を研ぎ澄ますことができるからです。
この記事では、【Step2:外部情報を知る】の第2弾として、業界動向と競合他社を分析するための具体的な視点と方法を解説します。
さあ、ライバルを知り尽くし、戦略の解像度を一気に上げましょう!
✓ なぜ業界動向・競合分析が知財戦略の鍵となるのか?
✓ 市場の今と未来を読むための視点と知財戦略への活かし方
✓ 業界の競争構造を掴む「5Force」の考え方と知財戦略への接続
✓ 競合他社の「実態」と「狙い」を把握する方法と知財戦略へのヒント
視点①:「市場」の今と未来を読む ~戦うフィールドを知る~


まず、自社が事業を展開する「市場」そのものを理解しましょう。
- 市場規模はどれくらいか?
今、その市場は大きいですか、小さいですか? 数値で把握することが重要です。 - 将来性はどう予測されるか?
今後、その市場は拡大しますか、縮小しますか? 成長率はどのくらいでしょうか。
これらの情報は、事業への力の入れ具合や、知財投資の規模を判断する上で基礎となります。
市場レポートや統計データを活用して調べてみましょう。
【知財戦略への接続】
成長市場であれば、新規参入者も増える可能性があります。
先行者としての利益を知財でどう守るかが重要になりますね。
逆に縮小市場であれば、限られたパイの中でどう生き残るか、あるいは新たな市場を創出するための知財戦略が必要になるかもしれません。
視点②:「業界構造」を掴む ~5つの力(5Forces)で競争環境を理解~
次に、その業界が「儲かりやすい構造」なのか、「厳しい競争環境」なのか。
それを理解するために、マイケル・ポーターの「5Force(ファイブフォース)分析」の視点が役立ちます。
これは、以下の5つの力から業界の魅力を分析する考え方です。
- 新規参入の脅威: 新しいプレイヤーが参入しやすいか?(参入障壁は高いか低いか)
- 代替品の脅威: 他の製品・サービスに取って代わられるリスクは?
- 買い手の交渉力: 顧客(バイヤー)の声は強いか?(価格決定権など)
- 売り手の交渉力: 部品・原材料供給元(サプライヤー)の声は強いか?
- 既存競合との敵対関係: 業界内の競争は激しいか?
これらの力が強いほど、その業界で利益を上げるのは難しくなります。
【知財戦略への接続】
この分析は、知財戦略と密接に関わります。
例えば、特許網は「新規参入の脅威」に対する強力な参入障壁になりえます。
交渉を有利に進めるための代替技術に関する知財は、「売り手」や「買い手」に対する交渉力を高めるかもしれません。
競合との敵対関係が激しいなら、クロスライセンスなどを活用した「抑止」戦略が重要になるでしょう。
業界構造を知ることで、知財を使って競争をどう有利に進めるか、その方向性が見えてきます。
(5Force分析の詳しい方法は、別の機会に解説しますね。)
視点③:「競合」を丸裸にする ~ライバルの実態と狙い~
さあ、いよいよ個別の「競争相手」=ライバルに迫りましょう。
彼らを深く知ることが、勝利への近道です。
- まず、誰が競合か?
直接的な競合だけでなく、間接的・潜在的な競合も含めてリストアップします。
Step1で洗い出した情報も活用しましょう。 - 競合は何をしている?(現状把握)
- 商品・サービス:
どんな特徴がありますか?
価格は? 顧客にどんな価値を提供していますか?(=競合の「選ばれる理由」は何か?) - 事業状況:
売上や利益はどうでしょうか? 勢いはありますか?(財務諸表、有価証券報告書など)
- 商品・サービス:
- 競合はどこへ向かう?(将来目論見)
- 新製品・新技術:
今、どんな開発を進めているでしょうか? 次にどんなものを出してきそうですか?
(HP、プレスリリース、特許出願情報、展示会など) - 事業戦略・ビジョン:
中長期的に何を目指していますか?
どんな会社になろうとしていますか?(統合報告書、IR情報、経営者の発言など)
- 新製品・新技術:
【知財戦略への接続】
競合分析から得られる情報は、知財戦略の宝庫です。
- 競合の強み・弱み(特に知財面)を把握し、自社の差別化ポイントを明確にできます。
「競合はこの技術の特許が弱いから、そこを攻めよう」といった戦略です。 - 競合の提供価値や将来目論見を知ることで、自社が取るべき対抗策や、逆に連携(共創)の可能性も見えてきます。
- 競合の新技術開発や特許出願動向は、将来の事業リスクを予測し、先手を打つために不可欠です。
「この分野で出願が増えているから、自社も対策が必要だ」といった判断ができます。
競合のIR情報などは、まさに宝の山かもしれません。ぜひチェックしてみましょう。
視点④:「自社の立ち位置」を再確認する ~分析結果を戦略へ~
市場、業界構造、そして競合。
これらの外部情報を分析することで、業界内における「自社の立ち位置」がより客観的に見えてきたはずです。
「我々の市場は成長しているが、競合A社の攻勢が激しいな」
「業界構造的に、サプライヤーへの依存が弱みになっている」
「競合B社は、我々が狙う次の市場にも既に出願を始めているようだ」
こうした現状認識こそが、効果的な戦略を立てるための土台となります。
ここまでの内部情報(Step1)と外部情報(Step2)の分析結果は、次のステップであるSWOT分析などで統合され、具体的な戦略オプションの創出へと繋がっていきます。
まとめ
今回は、【Step2:外部情報を知る】の第2弾として、業界動向と競合分析の重要性、そして具体的な視点と方法について解説しました。
- 市場の今と未来を読み、戦うフィールドを理解する。
- 業界構造(5Force)を掴み、競争環境を知る。
- 競合の実態と狙いを把握し、具体的な脅威と機会を発見する。
- 分析を通じて自社の立ち位置を客観的に認識する。
内部情報(自社の強みや課題)と、これらの外部情報を組み合わせることで、あなたの知財戦略の解像度は格段に上がり、より現実的で効果的なものになるはずです。
次のステップへ!
業界全体の動きと、主要な競合プレイヤーの状況が見えてきました。次は、競合が持つ「知的財産」にさらに焦点を当てて分析を進めます。
次回【Step2-3】では、競合他社の特許情報をどのように調査・分析し、自社の戦略に活かしていくか、その具体的なテクニックについて詳しく解説します。
こちらの記事もぜひ参照してください。
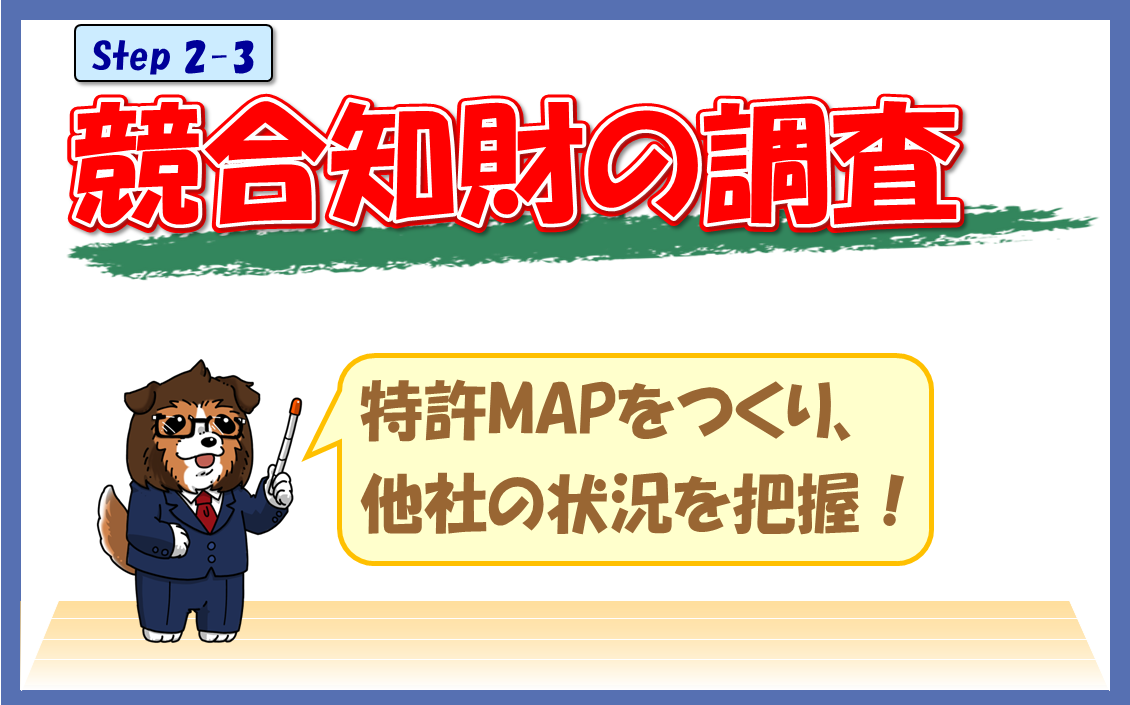
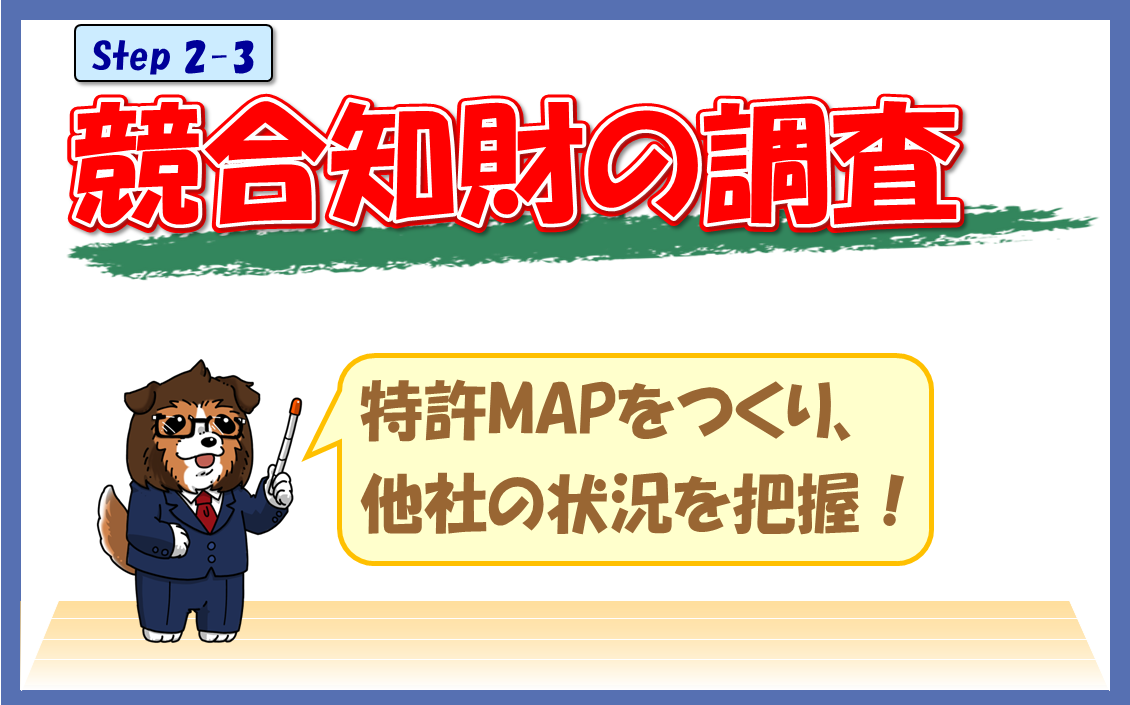
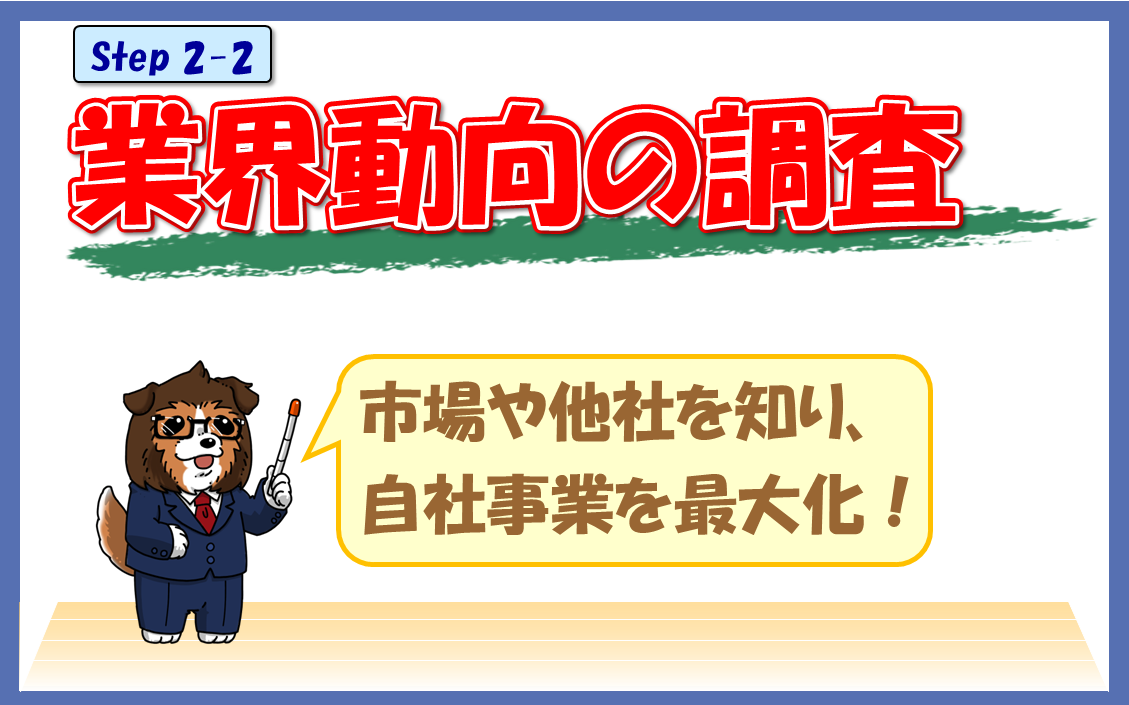

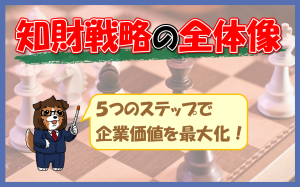
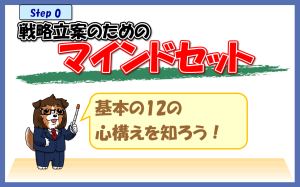
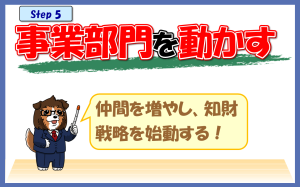
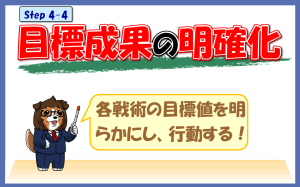
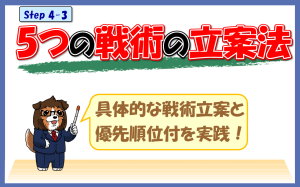
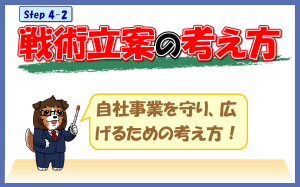
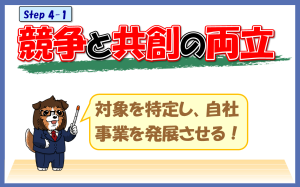
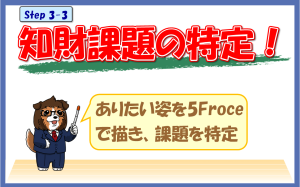
コメント