
内部や外部の情報の収集が終わり、ありたい姿を描いた後は、
何をしたらいいだろう。



そうだね。
次は、実際の「行動を決める」ことが大事だよ。



「行動を決める」か。段々現実的になってきたね。
でも、どうやってその行動を決めたらいいの?



よし、じゃあ今回は「行動を決める」ための考え方や
その方法について説明していくよ。
前回までの【Step3:将来を描く】で、あなたの会社の進むべき「ありたい姿」と、そこに到達するための課題が見えてきましたね。
素晴らしい羅針盤と課題リストが手に入りました!
さあ、ここからは【Step4:行動を決める】。
練り上げた戦略を「絵に描いた餅」で終わらせず、現実に変えるための具体的なアクションを設計していく重要なフェーズに突入です!
その行動計画を立てる上での最初の、そして最も重要な一歩が、「誰と戦い(=競争相手)、誰と組むか(=共創相手)」を明確に定めること。
なぜなら、どんなに優れた武器(技術や知財)を持っていても、戦う相手や協力する相手を見誤っては、戦略は空回りしてしまいます。
「自社の本当のライバルは誰だろう?」
「この『ありたい姿』を実現するために、誰の力を借りればジャンプアップできるだろうか?」
この記事を読めば、そんな疑問に答えを出せます。
自社の事業成長を加速させるために、戦略的に競争相手と共創相手を選び抜き、それぞれの「知的財産」を読み解いて具体的なアクションに繋げるための、実践的な考え方とヒントが得られます。
・なぜ今、競争相手と共創相手の特定が重要なのか?
・戦略的な競争相手の見つけ方(具体的な方法含む)
・競合の知財から戦略を読み解く分析テクニック
・事業を飛躍させる共創相手の見つけ方(具体的な方法含む)
・共創を成功に導くための相手の知財分析ポイント
1. 「敵」を知ることから始めよ!戦略的競合分析の思考法
まず、自社が戦うべき「競争相手」を特定しましょう。
これは単に「気に食わない相手」を探すことではありません。
なぜ競争相手を特定するのか?
- 自社の立ち位置を明確にするため: 広大な市場の中で、自社がどこで、誰と競っているのかを客観的に把握します。
- 戦略策定の重要なインプットを得るため: 競合の強み・弱み、戦略を分析することで、自社の採るべき戦略(差別化、集中など)が見えてきます。
- 将来的な脅威を早期に発見するため: 今は小さくても、将来大きな脅威となりうる競合の動き(特に技術や知財)をいち早く察知し、先手を打つことができます。
- 切磋琢磨による自社・業界の成長:健全な競争は、技術革新やサービス向上を促し、結果として自社と業界全体の発展につながります。
競争相手を特定するための「視点」
- 事業領域・技術の重なり具合:
- 直接競合: 同じ製品・サービスを提供(例:同じ機能のソフトウェア、同スペックの部品)
- 間接競合: 顧客ニーズは同じだが、提供方法が異なる(例:音楽CD vs 音楽配信サービス)
- 潜在的競合: 現在は異業種だが、将来参入してくる可能性(例:異業種からの技術転用、スタートアップ)
- 機会の損失・脅威の発生リスク:
- その企業の活動によって、自社の市場シェアが奪われる、または成長機会が失われるか?
- その企業の技術開発や特許取得によって、自社の事業継続や新規展開が脅かされるか?
実践!競争相手の見つけ方
- 市場調査: 業界レポート、ニュース記事、調査会社のデータを活用する。
- 顧客ヒアリング: 顧客が比較検討した製品やサービス、乗り換えの理由などを聞く。
- 展示会・業界イベント: 競合企業の出展内容や担当者の話を直接見聞きする。
- Web調査: 競合と思われる企業のWebサイト、プレスリリース、求人情報などをチェックする。
- 特許情報分析: 特定の技術分野(IPC分類など)やキーワードで検索し、活発に出願している企業(出願人)をリストアップする。 これは、水面下で技術開発を進めている潜在的競合を発見する上でも非常に有効です。
2. 競合の「武器庫」を探る!知財分析の実践テクニック
競争相手をリストアップしたら、次は彼らの「武器庫」=知的財産を分析し、その戦略や実力を探ります。
なぜ競争相手の知財を見るのか?
- 技術力・開発力の評価: どんな技術に注力し、どの程度のレベルにあるのかを把握します。
- 戦略・事業の方向性の推測: 特許出願の分野や内容から、彼らが次に狙っている市場や技術を予測します。
- 自社へのリスク評価: 自社の事業展開において、競合の特許が障壁とならないか(侵害リスクはないか)を確認します。
注目すべき知財の種類
- コア特許: 事業の根幹を成す技術に関する特許。権利範囲が広く、他社の参入を阻む「基本特許」である可能性も。
- 周辺特許: コア特許を補強・改良する技術。これらの厚みが、技術的な優位性を盤石にします。
- 出願動向: 特定分野への出願集中、出願件数の急増、国際出願(PCT、各国移行)の状況などから、戦略的な意図を読み解きます。
- 訴訟・審判履歴: 特許侵害訴訟や無効審判の経験は、その企業の知財に対する姿勢(攻撃的か、防御的か)や、権利の強さを示す指標となり得ます。
実践!競合知財の分析方法
- 特許データベースの活用: J-PlatPat(日本)、Espacenet(欧州)、Google Patents、USPTO(米国)などを活用し、出願人名、技術キーワード、IPC/CPC分類を組み合わせて検索します。
- 特許分析ツールの利用: 件数推移、技術マップ、引用関係などを可視化するツール(有料・無料あり)を使えば、効率的に全体像を把握できます。(例:パテントマップ作成機能など)
- 分析の観点:
- 権利の強さ・広さ: 請求項の記載、引用/被引用関係、審査経過(拒絶理由への応答など)、権利維持状況(年金納付)を確認します。
- 技術分野の注力度: 特定の技術分類への出願集中度合いや、時系列での変化を見ます。
- 出願の質と戦略性: 個々の特許内容だけでなく、ポートフォリオ全体としてどのような戦略(例:包囲網形成、特定分野の独占)が見えるかを考察します。
- リスク評価: 自社製品・技術との関連性が高い特許がないか、特に注意して確認します(侵害予防調査)。
- 専門家の活用: 高度な分析やリスク評価が必要な場合は、弁理士や特許調査会社など、専門家の知見を借りることも有効です。
3. 「共に未来を創る」共創相手を探す思考法
競争だけが戦略ではありません。
自社だけでは成し遂げられない目標を達成するために、「共創相手」=パートナーを探すことも、現代の知財戦略において極めて重要です。
なぜ共創相手が必要なのか? (オープンイノベーションの視点)
- 自社リソースの補完: 不足している技術、販路、ブランド力、生産能力などを、外部の力で補います。
- 開発スピードの向上: 共同開発や技術導入により、製品・サービスをより早く市場に投入できます。
- イノベーションの創出: 異なる強みを持つ組織が連携することで、単独では生まれなかった新しい発想や価値(=イノベーション)が生まれる可能性が高まります。
- リスクの分散: 新規事業開発など、不確実性の高い挑戦において、リスクや投資負担を分担できます。
共創相手を特定するための「視点」
- 事業領域・技術領域の補完性:
- 自社の弱みを補い、強みをさらに伸ばせる技術やノウハウを持っているか?
- 自社の技術と組み合わせることで、新たな価値を生み出せるか?(完全に同じ領域より、隣接・補完領域が有望な場合が多い)
- 強みの強化・弱みの補強可能性:
- 相手の販路やブランド力を活用して、自社製品・サービスの展開を加速できるか?
- 相手の生産能力を活用して、コスト削減や安定供給を実現できるか?
- 相手の保有特許を活用して、自社の技術的課題を解決したり、製品の付加価値を高めたりできるか?
実践!共創相手の見つけ方
- 自社のニーズ・課題の明確化: まず「何が足りないのか」「何を実現したいのか」を具体化します。技術ロードマップや課題リストが役立ちます。
- 技術探索: 学会発表、論文、技術展示会、業界ニュースなどで、有望な技術を持つ企業や研究機関を探します。
- オープンイノベーションプラットフォーム: AUBA、Creww、eiiconなどのプラットフォームを活用し、自社のニーズを発信したり、他社の提案を探したりします。
- 大学・公的研究機関との連携: 基礎研究や応用研究レベルでの連携を探ります。
- 特許情報分析: 自社が必要とする技術分野や、自社技術と補完関係にある技術分野で、質の高い特許を持つ企業や大学を探します。
4. 共創相手の「知財」を活かす!連携成功のための分析
有望な共創相手候補が見つかったら、その企業の知的財産を分析し、連携の可能性とリスクを評価します。
なぜ共創相手の知財を見るのか?
- 連携によるシナジー効果の評価: 相手の知財(特許、ノウハウ、ブランド)が、自社の事業や技術とどれだけ効果的に組み合わせられるかを見極めます。
- 技術レベルと信頼性の確認: 特許情報などから、相手の技術開発力や専門性を客観的に評価します。
- 連携に伴うリスクの事前評価: 共同開発における権利の取り扱いや、既存権利との抵触リスクなどを事前に把握します。
注目すべき知財の種類
- 補完的な特許: 自社の特許技術と組み合わせることで、より強力な製品・サービスや、新たなイノベーションを生み出す可能性のある特許。
- ノウハウ・営業秘密: 特許化されていないが価値のある技術情報、製造プロセス、顧客データなど。(これは外部から直接知ることは困難ですが、連携交渉の中で重要になります)
- ブランド力・商標: 認知度や信頼性の高いブランドは、共同製品やサービスの価値を高めます。
実践!共創相手の知財分析
- 特許ポートフォリオ分析: 相手企業の特許全体を俯瞰し、技術分野の分布、注力領域、自社技術との補完性などを評価します。
- 技術デューデリジェンス(連携具体化時): 共同開発やライセンス契約の前には、対象となる特許や技術の有効性、権利範囲、他社権利との抵触リスク(FTO)などを詳細に調査・評価します。これは非常に重要です。
- 分析の観点:
- 技術的な補完性と新規性: 単なる足し算ではなく、掛け算(1+1が3以上)になるような組み合わせか?
- 権利関係のクリアランス: 共同開発や技術導入にあたり、第三者の権利を侵害するリスクはないか? ライセンス条件は明確か?
- 連携への姿勢: 過去のライセンス実績や共同開発経験などから、オープンイノベーションに対する意欲や姿勢を推測します。
- シナジーの具体性: 連携によって、具体的にどのような製品・サービスが生まれ、どのような市場価値が期待できるか?
競争と共創のダイナミズム
今日のビジネス環境では、ある分野では激しく競争する相手が、別の分野では協力して新しい価値を創る共創相手になることも珍しくありません。
固定観念にとらわれず、常に状況を注視し、最適な関係性を模索する視点も重要です。
5. まとめ:「相手」を知り、「己」を知り、次なる「行動」へ
お疲れ様でした!
今回は、【Step4:行動を決める】の第一歩として、事業成長の鍵を握る「競争相手」と「共創相手」を特定し、それぞれの知的財産を分析するための考え方と実践的なヒントを解説しました。
誰と戦い、誰と組むかを定めることは、絵に描いた戦略を「実行可能な計画」へと落とし込むための、極めて重要な基礎工事です。
本記事を参考に、ぜひ自社の競争相手と共創相手をリストアップし、それぞれの知財状況を分析してみてください。
その分析結果、すなわち「相手を知り、己を知る」ことから得られる洞察が、次の具体的な『戦法』を考える上での強力な武器となるはずです。
次回:【Step4-2:戦法を立案するための考え方】へ
さて、戦う相手と組む相手が見えてきましたね。
では、これらの相手に対して、あるいは市場全体に対して、自社の「ありたい姿」を実現するために、どのような具体的な戦い方・組み方(=知財戦略オプション)を繰り出すべきでしょうか?
次回【Step4-2:戦法を立案するための考え方】では、今回の分析結果を踏まえ、攻め(権利行使、ライセンスアウトなど)と守り(権利取得、クリアランス、防衛公開など)、そして協調(共同開発、ライセンスインなど)といった、多様な知財戦略オプションを発想し、選択するための考え方について掘り下げていきます。
今回の分析結果という武器を手に、ぜひ次のステップへ進みましょう!
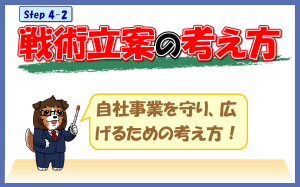
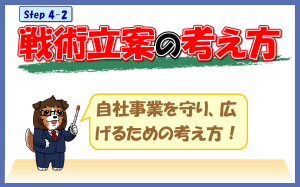
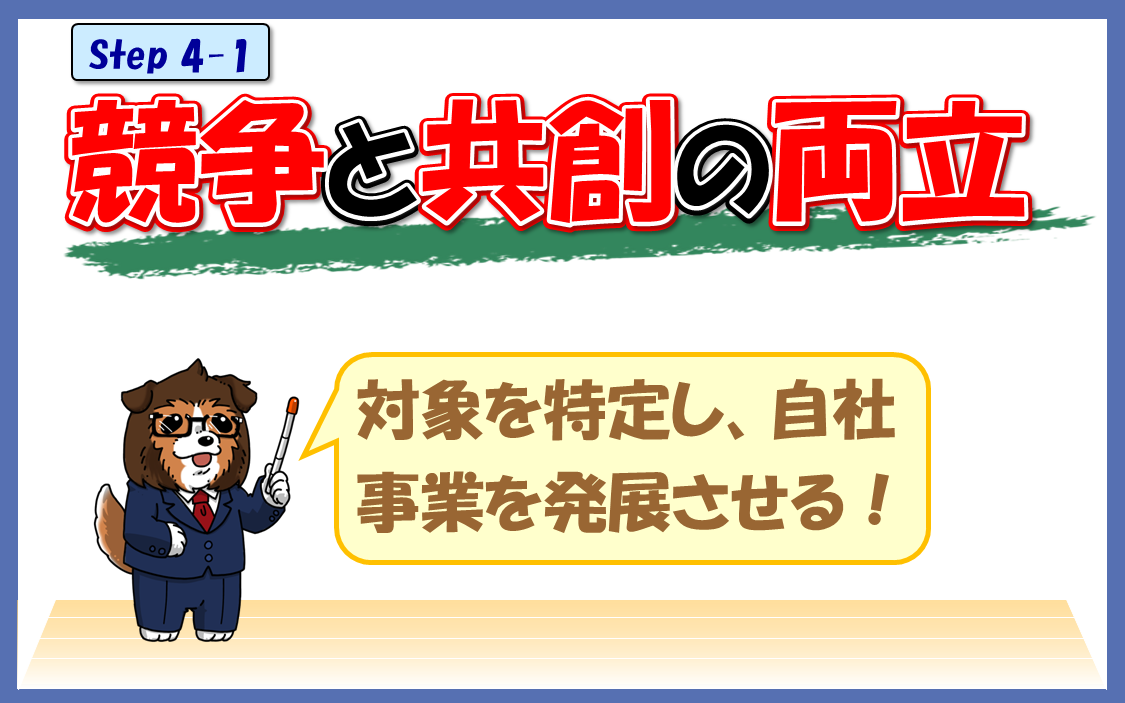

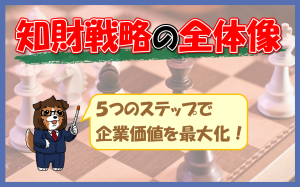
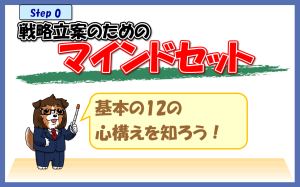
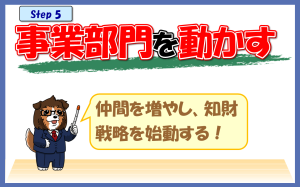
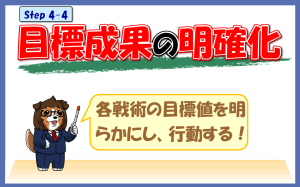
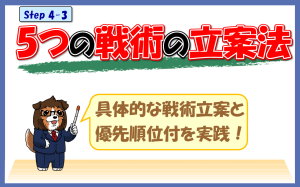
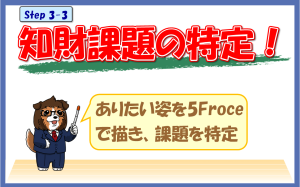
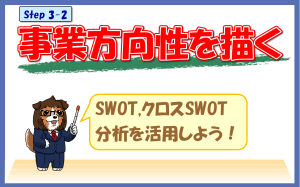
コメント