
「ありたい姿」を思い描くように言われたんだけど、
どう考えればいいか、さっぱりわからなくて。。。



確かに、まっさらな所から描くのは難しいよね。
でも、そのためのいい方法があるんだ。



えっ!それは何なの?
教えて!!



それは、「SWOT」分析と「クロスSWOT」分析を行うことだよ。
今回は、これについて詳しく解説していくよ。
「うちの会社の強みって、本当は何だろう?」
「新しい市場に挑戦したいけど、何から手をつければ…」
「競合の動きが早くて、将来が不安…」
企業の経営者や事業責任者の皆さま、自社の未来を描く上で、こんな漠然とした課題を感じていませんか?
変化の激しい時代、持続的な成長を実現するには、自社の進むべき明確な方向性、すなわち「ありたい姿」を描き、そこに向かって戦略的にリソースを投下していくことが不可欠です。
しかし、勘や経験だけに頼った戦略立案には限界があります。そこで役立つのが、自社の現状と取り巻く環境を客観的に分析する「SWOT分析」と、具体的な戦略オプションを導き出す「クロスSWOT分析」です。
「SWOT分析は知ってるけど、具体的にどう事業戦略や未来像に結びつけるの?」
「分析したのはいいけど、結局どう行動すればいいかわからない…」
そんな声もよく聞かれます。
本記事は、知財戦略立案の前提となる【Step3:将来を描く】の第2弾です。
今回はより事業全体の視点から、SWOT分析・クロスSWOT分析を活用して会社の「ありたい姿」を描き出す方法を解説します。
そして、そのプロセスにおいて、知的財産(知財)がどのように影響し、武器となり得るのかについても触れていきます。
この記事を読めば、あなたの会社の事業が目指すべき「ありたい姿」をより具体的に描き、実現に向けた戦略的な第一歩を踏み出すためのヒントが得られるはずです。
✓ なぜ事業全体の「ありたい姿」を描くためにSWOT分析が有効なのか?
✓ 自社の「強み」「弱み」「機会」「脅威」を事業視点で洗い出す方法
✓ 分析結果から具体的な「事業戦略オプション」を導き出す方法(クロスSWOT分析)
✓ その戦略において「知財」がどのように関わり、貢献できるのか?
なぜ事業の「ありたい姿」を描くためにSWOT分析が必要なのか?
SWOT分析は、自社の内部環境(Strength: 強み、Weakness: 弱み)と外部環境(Opportunity: 機会、Threat: 脅威)を整理する、事業戦略立案の基本的なフレームワークです。
これを活用することで、以下のようなメリットがあります。
・自社の現在地を客観的に把握:
思い込みや勘ではなく、事実に基づいて自社のリソースや市場での立ち位置を冷静に見つめ直せます。
・事業を取り巻く環境変化の把握:
市場のトレンド、競合の動き、技術革新、法規制の変化など、自社に影響を与える外部要因を整理できます。
・戦略的な意思決定の土台:
どこに経営資源を集中させ、どのリスクに備えるべきか、といった重要な判断の根拠となります。
そして、この事業全体の分析において、知的財産(知財)は無視できない重要な要素です。なぜなら、
・「強み」を支える柱:
優れた技術力やブランド力の背景には、多くの場合、特許や商標といった知財が存在します。
・「弱み」の原因やボトルネック:
新製品開発の遅れが、他社特許の存在や、自社の権利確保の不備に起因しているかもしれません。
・「機会」を活かすための鍵:
新技術トレンドに合わせた戦略的な特許取得、保有知財のライセンスにより、新たな収益源を生み出せます。
・「脅威」そのもの、または脅威への対抗手段:
競合他社の特許戦略や、特許侵害訴訟のリスクは事業継続の脅威ですが、
自社の強固な知財ポートフォリオは対抗手段となり得ます。
つまり、事業の「ありたい姿」を描く上で、知財の状況を正しく認識し、戦略に組み込むことは、その実現可能性や競争優位性を大きく左右するのです。SWOT分析は、そのための出発点となります。
SWOT分析:事業と知財の現状を徹底解剖
では、実際に事業全体の視点でSWOT分析を進める手順と、知財がどう関わるかを見ていきましょう。
Step 1: 分析対象の明確化
どの事業(または会社全体)の「ありたい姿」を描きたいのか、対象を明確にします。
Step 2: 情報収集
事業に関する内部情報(売上・利益データ、顧客基盤、製品・サービスの特徴、技術力、組織体制、人材、ブランド認知度など)を収集します。
あわせて、外部情報(市場規模・成長性、競合動向、顧客ニーズの変化、技術トレンド、経済情勢、法規制など)も幅広く収集します。
この際、自社や競合の知財情報(特許出願状況、保有権利、ライセンス動向など)も重要な情報源となります。
情報収集については、過去のこちらの記事も参考にしてください。
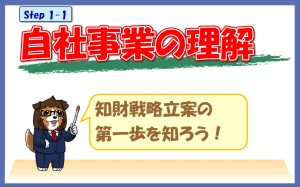
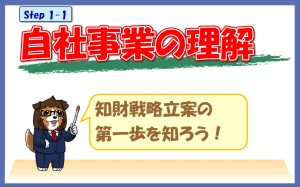
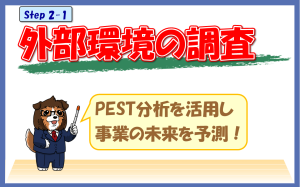
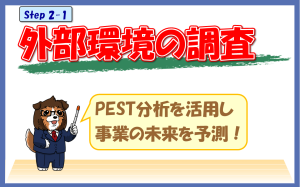
Step 3: SWOTマトリックスの作成
収集した情報を、以下の4つのカテゴリーに分類します。
事業全体の視点で書き出し、関連する知財要素があれば補足的に記述します。
【事業戦略に役立つ! SWOT各要素の具体例】
| 強み(Strength): ・主力製品における高い市場シェア(背景:長年のブラン ド信頼性、差別化技術に関する基本特許) ・効率的な生産プロセスによるコスト競争力 (背景:独自ノウハウの徹底管理、関連製造装置特許) ・優秀で経験豊富な研究開発チーム (背景:継続的なイノベーションと特許創出力) ・強い顧客ロイヤリティとリピート率 (背景:高品質な製品・サービス、信頼のブランド) ・特定地域での強固な販売網 | 機会(Opportunity): ・〇〇市場の急速な成長 (例:アジア市場、環境配慮型製品市場など) ・AI、IoTなどの新技術トレンドの活用可能性 (→ 関連技術導入、自社技術との融合、新規特許出願) ・異業種企業との戦略的提携の可能性 (→ 共同開発、技術ライセンス、知財の相互活用) ・規制緩和による新規参入障壁の低下 ・競合企業の経営不振や事業撤退 |
| 弱み(Weakness): ・特定の顧客層への依存度が高い ・新製品の市場投入までのリードタイムが長い(原因:開発プロセス、他社特許のクリアランスに時間がかかる等) ・デジタルマーケティング・オンライン販売チャネルの立ち遅れ ・次世代の経営・技術リーダー人材の不足 ・海外市場でのブランド認知度が低い (原因:商標権の未取得、現地でのプロモーション不足) | 脅威(Threat): ・価格競争の激化、コモディティ化の進行 ・新規参入企業による破壊的イノベーション (→ 自社の既存技術・特許が無効化されるリスク) ・主要な原材料価格の高騰、サプライチェーンの不安定化 法規制の強化(環境規制、個人情報保護など) ・景気後退による消費マインドの冷え込み ・競合他社からの特許侵害訴訟のリスク、警告 |
Step4:分析のポイントと注意点
SWOT分析をする際は、次のことに注意して行うとよいでしょう。
✓ 客観性:
希望的観測や思い込みを排除し、事実に基づいて評価します。
✓ 多角的な視点:
経営層、知財担当、研究開発、営業など、様々な部門からの意見を取り入れます。
✓ 具体性:
抽象的な表現ではなく、具体的な事実やデータを記述します。
分析から行動へ!「クロスSWOT分析」で事業戦略オプションを創る
SWOT分析で現状を把握したら、
次はその結果を組み合わせて具体的な事業戦略オプションを創り出す「クロスSWOT分析」に進みます。
これは、洗い出した各要素を掛け合わせることで、より実践的な打ち手を検討する手法です。
以下の4つの組み合わせから、自社が取るべき戦略の方向性を考えます。
ここでも、具体的な知財アクションを意識することが重要です。
【クロスSWOT分析:4つの戦略方向性(事業戦略オプション例と知財の役割)】
| 機会(Opportunity): | 脅威(Threat): | |
| 強み(Strength): | 強み(S) × 機会(O) = 積極的事業拡大戦略 考え方: 自社の強みを活かして、市場の機会を最大限に捉える。 事業戦略オプション例: ・高い市場シェア(S)を持つ主力製品を、成長中の海外市場(O)に投入する。(知財の役割: 現地での商標・特許出願、模倣品対策) ・優秀なR&Dチーム(S)を活かし、新技術トレンド(O)を取り込んだ次世代製品を開発し、市場をリードする。(知財の役割: 開発初期からの戦略的な特許網構築、標準化への関与) ・強固な販売網(S)を活用し、有望な提携候補(O)の製品・サービスを共同で展開する。(知財の役割: ライセンス契約、共同ブランド戦略) | 強み(S) × 脅威(T) = 差別化・防衛戦略 考え方: 強みを活用して、脅威の影響を回避・軽減する。 事業戦略オプション例: ・コスト競争力(S)を武器に、価格競争の激化(T)の中でも利益を確保できる事業構造を維持する。(知財の役割: 製造プロセスノウハウの保護強化、さらなる効率化技術の開発・権利化) ・高いブランド信頼性(S)を活かし、新規参入の脅威(T)に対して顧客のスイッチングを防ぐ。(知財の役割: ブランド価値維持のための継続的な品質管理、模倣品対策) ・特許侵害訴訟のリスク(T)に対し、自社の強固な特許ポートフォリオ(S)を交渉材料に有利な解決を図る(クロスライセンスなど)。 |
| 弱み(Wakess): | 弱み(W) × 機会(O) = 弱点克服・新規分野挑戦戦略 考え方: 弱みを補強・改善しながら、機会を活かす方法を探る。 事業戦略オプション例: ・デジタル対応の遅れ(W)を、外部の専門企業との提携(O)によって補い、オンライン販売を強化する。(知財の役割: システム利用契約、データ利用に関する取り決め) ・新製品開発の遅さ(W)を、有望な技術を持つスタートアップへの出資やM&A(O)によって解消する。(知財の役割: 知財デューデリジェンス、権利の承継・活用戦略) ・海外での認知度の低さ(W)を、成長市場(O)にターゲットを絞ったブランディング投資で克服する。(知財の役割: 現地での商標調査・出願、ブランド保護戦略) | 弱み(W) × 脅威(T) = 事業見直し・リスク回避戦略 考え方: 弱みと脅威が重なる領域でのダメージを最小限に抑える。 事業戦略オプション例: ・依存度の高い顧客層(W)が景気後退(T)の影響を受けやすい場合、新たな顧客セグメントを開拓する。 ・収益性が低く(W)、将来性も乏しい(T)事業からは段階的に撤退し、経営資源を成長分野に再配分する。(知財の役割: 関連する特許等の権利の放棄・売却判断) ・他社特許の脅威(T)があり、かつ自社の技術的優位性が低い(W)分野では、開発方針を変更し、侵害リスクを回避する(デザインアラウンド)。 |
分析のポイントと注意点
クロスSWOT分析をする際は、次のことに注意して行うとよいでしょう。
✓ 具体性:
各戦略オプションを、具体的なアクションプランに落とし込みます。
✓ 優先順位付け:
すべてを実行するのは困難です。経営目標との整合性、実現可能性、リスク、期待される効果などを考慮し、優先順位をつけます。
戦略の選択と実行:事業の「ありたい姿」を描く
クロスSWOT分析で見えてきた様々な事業戦略オプション。
これらを検討し、「自社は将来どうなっていたいのか?」という問いに対する答え、すなわち事業全体の「ありたい姿」を具体化していきます。
- 3年後、5年後、どの市場でリーディングカンパニーになっていたいか?
- 顧客から、社会から、どんな存在として認識されたいか?
- どのような企業文化を持ち、従業員がどのように働いている状態を目指すか?
この「ありたい姿」こそが、今後の事業戦略、そしてそれを支える研究開発戦略、マーケティング戦略、人材戦略、そして知的財産戦略の拠り所となる北極星です。
知財戦略は、「ありたい姿」を実現するために、知財をどのように創造・保護・活用していくかを定めるもの。
事業全体の大きな方向性が見えて初めて、意味のある知財戦略を描くことができるのです。
まとめ:客観的な分析から、未来への確かな一歩を
今回は、事業全体の「ありたい姿」を描くためのツールとして、SWOT分析とクロスSWOT分析の活用法を、知財の役割も踏まえながら解説しました。
この分析を通じて得られるもの:
- 事業全体の客観的な現状認識(強み、弱み、機会、脅威)
- 目指すべき「ありたい姿」に繋がる事業戦略の選択肢
- 各戦略における知財の位置づけと活用の方向性
- 組織内での目指す方向性に関する共通認識
分析を成功させるカギ:
- 事業全体の視点を常に持つこと。
- 知財を「事業を構成する重要な要素」として捉えること。
- チームで議論し、多様な視点を取り入れること。
- 定期的な見直しを怠らないこと。
さあ、まずはあなたの会社の現状をSWOT分析で整理し、未来への羅針盤となる「ありたい姿」を描くことから始めてみませんか?
そのプロセスは、きっと貴社の未来をより明るく、確かなものにするはずです。
次回予告:【Step3-3 ありたい姿の特定】へ
SWOT分析・クロスSWOT分析で、「ありたい姿」の方向性が見えてきました。
しかし、その「ありたい姿」を実現する上で、業界特有の競争要因はどのように影響するのでしょうか?
また、乗り越えるべき具体的な事業課題は何でしょうか?
次回【Step3-3 ありたい姿の特定】では、業界構造を分析する「5Forces(ファイブフォース)分析」を用いて、これらの点をさらに深掘りし、「ありたい姿」をよりシャープに特定していきます。
今回描いた「ありたい姿」のイメージを胸に、ぜひ次のステップへお進みください!
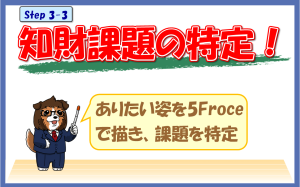
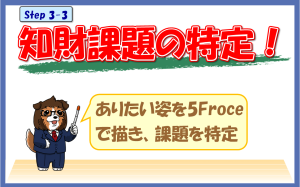
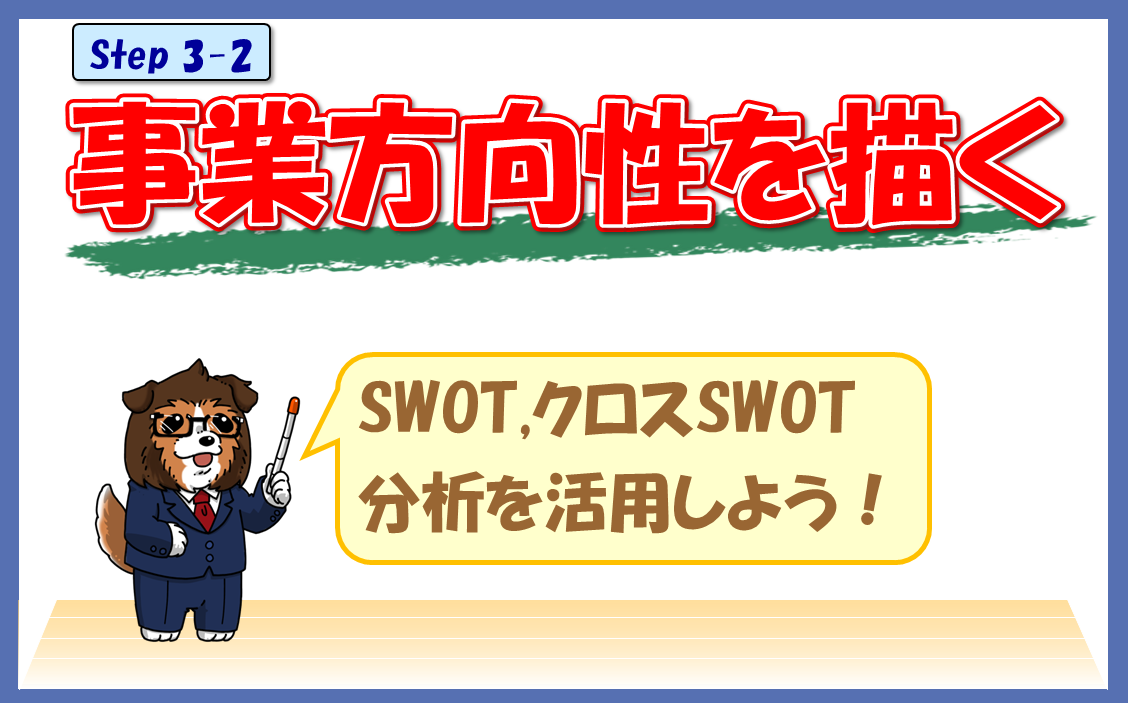

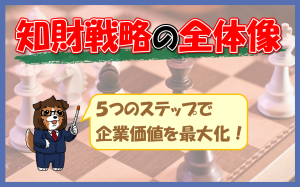
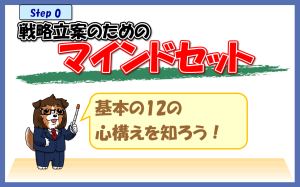
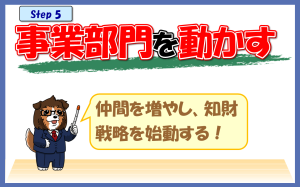
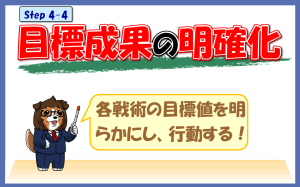
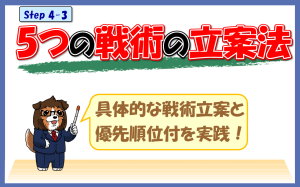
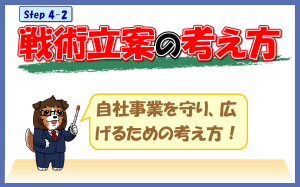
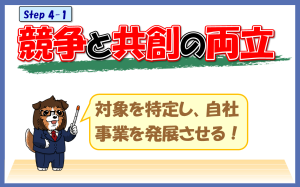
コメント