
知財戦略ってよく言いますけど、具体的に何をすればいいんですか?



そうだですね。まずは自社の事業を守り、成長させるための”戦い方”を知ることから始めましょう。大きく分けて5つの方法があります。



5つの方法でうか?なんだか難しそうですが...
具体的にはどんなことでしょうか?



簡単に言うと、攻めと守りの戦略です。模倣を防いだり、逆に他社の権利に対抗したり...。
この記事で詳しく解説しているので、一緒に見ていきましょう。
前回【Step4-2】では、知財戦術を立案するための「思考の軸」を学びましたね。「ありたい姿」実現のため、「お客様に選ばれる」ことを目指し、「攻め・守り・協調」のスタンスを考える。その重要性をご理解いただけたかと思います。
さあ、今回はさらに具体的に進みます。**【Step4:行動を決める】**の第3弾として、前回学んだ思考の軸に基づき、実際にどのような「戦法」の引き出しがあるのかを知り、それをどう選び、どう組み合わせていくか、その考え方を解説します。
前回特定した「競争相手」や「共創相手」。これらの**「相手」を常に念頭に置き**、自社の状況に合わせて最適な戦法を選択することが、戦略成功のカギとなります。
この記事を読めば、知財戦略における**代表的な5つの戦法(武器)**を理解できます。そして、自社の状況に合わせてどの武器を、どの順番で使うべきか、その優先順位付けの考え方も身につきます。「よし、自社の戦術プランを具体化しよう!」と感じていただけるはずです。
✓ 知財戦略で使える5つの具体的な戦法(牽制、抑止、折衝、対処、諜報)
✓ 各戦法を「どの相手に」「何のために」使うのか
✓ 戦術の優先順位をつける際の具体的な考え方
知財戦術の5つの武器:「牽制」「抑止」「対処」「折衝」「諜報」
「ありたい姿」へ向かう道のりには、様々な障害やチャンスがあります。
それらに的確に対応するために、私たちは知財戦略における具体的なアクションを、大きく5つの「戦法」(武器)として整理しました。
- 牽制 (けんせい): 相手の動きを封じる盾と矛
- 抑止 (よくし): 争いを未然に防ぐ相互の鎖
- 対処 (たいしょ): 障害物を除去・回避する技術
- 折衝 (せっしょう): 交渉で価値を共創する握手
- 諜報 (ちょうほう): 情報とルールで流れを作る羅針盤
この5つの武器の概要を表で確認しましょう。
それぞれの武器が、「何を目指し(目的)」「誰に対して使うことが多く(主な対象)」「具体的に何をするのか(キーワード)」を示しています。
【知財戦術 5つの武器 要約表】
| 戦法 | 主な目的 | 主な対象 | キーワード(アクション例) |
| ① 牽制 | 模倣・参入の抑止 自社の優位性確保 | 競争相手 | 権利取得、権利の壁、侵害警告姿勢、 模倣意欲減退 |
| ② 抑止 | 相手からの権利行使の防止 事業自由度の確保 | 競争相手 | クロスライセンス用特許、相互牽制、 訴訟回避、交渉促進 |
| ③ 対処 | 相手権利リスクの低減・無力化 事業自由度の確保 | 競争相手の権利 | 回避設計 、情報提供、 異議申立、無効審判、鑑定 |
| ④ 折衝 | 連携による価値共創 リソース補完、開発効率化 | 共創相手 (時に競合も) | 共同開発、ライセンス交渉 (イン/アウト)、 契約締結、Win-Win |
| ⑤ 諜報 | 有利な事業環境の構築 情報収集、ルール形成、機会探索 | 市場、業界、行政、 相手候補 | パートナー探索、ロビー活動、標準化、 世論形成、情報分析 |
ポイント:
- これらの武器は独立しているわけではなく、相互に関連し合います。
- どの武器を、どの相手に、どのタイミングで使うかが「戦略」となります
【対 競争相手】主導権を握り、リスクを減らす戦法
まずは、主に「競争相手」に対して有効な3つの武器です。
武器① 牽制:模倣・参入を思いとどまらせる
「牽制」は、競争相手が安易にこちらの市場に参入したり、技術を模倣したりすることを思いとどまらせるための戦法です。いわば、攻めにも守りにも使える盾と矛のようなものです。
- 目的: 模倣阻止、参入障壁の構築、技術的優位性の誇示。
- 相手: 主に競争相手(既存・潜在)。
- 具体的な活動例:
- 自社のコア技術や改良技術について特許権や意匠権などを取得し、権利の壁を築きます。
- 単に権利を持つだけでなく、権利侵害に対しては断固たる措置をとる姿勢を示すことも重要です。「模倣すれば痛い目に遭う」と思わせることが牽制力となります。
- 例えば、競合A社の類似製品開発の動きを察知したら、関連特許の出願を強化し、警告を発することも「牽制」の一環です。
武器② 抑止:相手の攻撃を封じ、自由を確保する
「抑止」は、競争相手が保有する特許権などを、自社に対して行使してくることを防ぐための戦法です。
いわば、互いに武器を向け合い、撃ち合いを避けるための「相互の鎖」です。
- 目的: 相手からの権利行使リスク低減、事業の自由度確保、訴訟回避。
- 相手: 主に特定の競争相手(特に多くの特許を持つ相手)。
- 具体的な活動例:
- クロスライセンス交渉の材料となる特許を取得します。相手の事業に影響を与えうる特許を持つことで、交渉を有利に進められます。
- 自社事業の周辺領域にも特許網を張っておきます。これにより、「もしこちらを攻撃するなら、こちらもあなたの事業を攻撃できる」という状況を作り出します。
- 例えば、競合B社が強力な特許を持つ場合、こちらもB社の事業に関連する特許を取得し、「相互不可侵」の関係を築くことを目指します。
武器③ 対処:相手の権利リスクを無力化する
「対処」は、競争相手が持つ特許権などが、自社の事業活動の障害となる場合に、そのリスクを低減・無力化するための戦法です。
障害物を除去したり、回避したりする技術と言えます。
- 目的: 侵害リスクの回避・低減、事業の自由度確保。
- 相手: 主に競争相手が保有する権利。
- 具体的な活動例:
- 懸念される相手の特許を**回避するための設計変更(デザインアラウンド)**を行います。
- 相手が出願中の特許に対して、先行技術などの情報提供を行い、権利化を阻止・制限します。
- 登録されてしまった権利に対しては、異議申し立てや無効審判を請求し、権利の取り消しや無効化を目指します。
- 専門家による鑑定で、非侵害の主張や権利の弱点を見つけ出すことも有効です。例えば、競合C社の気になる特許が見つかったら、まず無効化できないか検討します。
【対 共創相手/市場】連携と環境整備で飛躍する戦法
次に、主に「共創相手」との連携や、「市場」全体に働きかける2つの武器です。
武器④ 折衝:交渉で共に価値を創る
「折衝」は、特定の他社(主に共創相手)と交渉を行い、協力関係を築くための戦法です。
Win-Winの関係を目指し、事業の成長を加速させるための「握手」と言えます。
- 目的: 共同での価値創造、リソース補完、開発効率化。
- 相手: 主に共創相手。(場合によっては競争相手との和解交渉なども含む)
- 具体的な活動例:
- 共同研究開発の契約交渉を行います。成果の権利帰属や実施条件などを明確に定めます。
- 他社が保有する優れた特許技術のライセンスイン交渉を進めます。これにより、自社の開発時間やコストを削減できます。
- 例えば、有望な技術を持つスタートアップD社と、共同開発のための条件交渉を行うのが「折衝」です。
武器⑤ 諜報:情報とルールで有利な場を作る
「諜報」は、単なる情報収集に留まらず、市場のルール形成や世論にも働きかけ、自社にとって有利な事業環境を作り出すための戦法です。
未来を見据え、流れを作るための「羅針盤」や「舵取り」のイメージです。
- 目的: 有利な事業環境の構築、将来の機会・脅威の早期発見、共創機会の探索。
- 相手: 市場全体、業界、行政、潜在的な共創相手など。
- 具体的な活動例:
- 将来有望な共創相手となりうる企業や研究機関を探索します。
- 業界団体や標準化団体、行政機関に働きかけ、自社技術に有利な規格やルール、法規制の形成を目指します。(ロビー活動)
- 学会発表や論文発表、広報活動を通じて、自社技術の優位性やビジョンを社会に発信し、有利な世論を形成します。
どの武器を、いつ使う?「優先順位付け」の考え方
紹介した5つの武器。
これら全てを同時に、全力で実行するのは現実的ではありません。
リソース(人・物・金・時間)は有限です。
だからこそ、どの戦法に、どのタイミングで注力するのか、「優先順位付け」が極めて重要になります。
優先順位を決める際には、以下の点を考慮しましょう。
- 「ありたい姿」へのインパクト: その戦法は、目標達成にどれだけ貢献するか?
- 緊急度: 今すぐ取り組まないと、手遅れになるリスクはないか?
- 競合・共創相手の状況: 相手の動きや関係性に合わせて、有効な手は何か?
- 自社の事業フェーズ: 導入期か成長期か? スタートアップか大企業か?
- 利用可能なリソース: 実行に必要な人員、予算、時間は確保できるか?
例えば、これらの要素を「インパクト(重要度)」と「緊急度」の2軸でマトリクス評価し、優先的に取り組むべき戦術(右上に来るもの)を可視化するのも一つの手です。
あるいは、設定したKPI(重要業績評価指標)と連動させ、KPI達成に直結する戦術の優先度を上げる、という考え方もあります。
スタートアップなら、まず「牽制」でコア技術を守ることが最優先かもしれません。
一方、成熟企業なら、「抑止」による安定確保や、「折衝」「諜報」による新たな成長機会探索の重要度が増すでしょう。
まとめ:武器を選び、組み合わせ、勝利への道筋を描こう!
今回は、知財戦略における具体的な5つの戦法(武器)、「牽制」「抑止」「対処」「折衝」「諜報」について、その内容と選び方の考え方を解説しました。
これらの武器は、単独で使うだけでなく、状況や相手に応じて戦略的に組み合わせることで、その真価を発揮します。
どの武器を、どのタイミングで、どの相手に対して使うのか。それを考えることが、まさに知財「戦略」です。
自社の「ありたい姿」を実現するために、そして「お客様に選ばれる」存在であり続けるために。
これらの武器をどう使いこなすか、ぜひ考えてみてください。
次回:【Step4-4:目標設定と成果測定で知財戦略の確実な成功へ】へ
さあ、使うべき武器(戦法)のイメージが湧いてきましたね。
次は、いよいよその武器をどう使いこなし、確実に成果に繋げるか、という実行計画のフェーズです!
次回【Step4-4】では、選定した戦術に基づいて、具体的な目標(KGI/KPI)を設定し、その進捗と成果をどのように測定・評価していくか、戦略の実行力を高めるための方法について詳しく解説します。
今回選んだ武器を手に、勝利への最後の詰めを行いましょう!
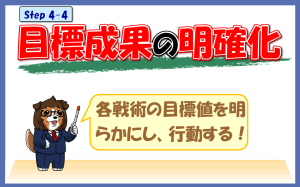
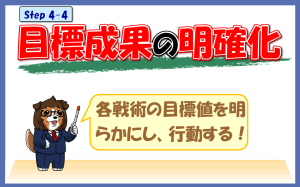
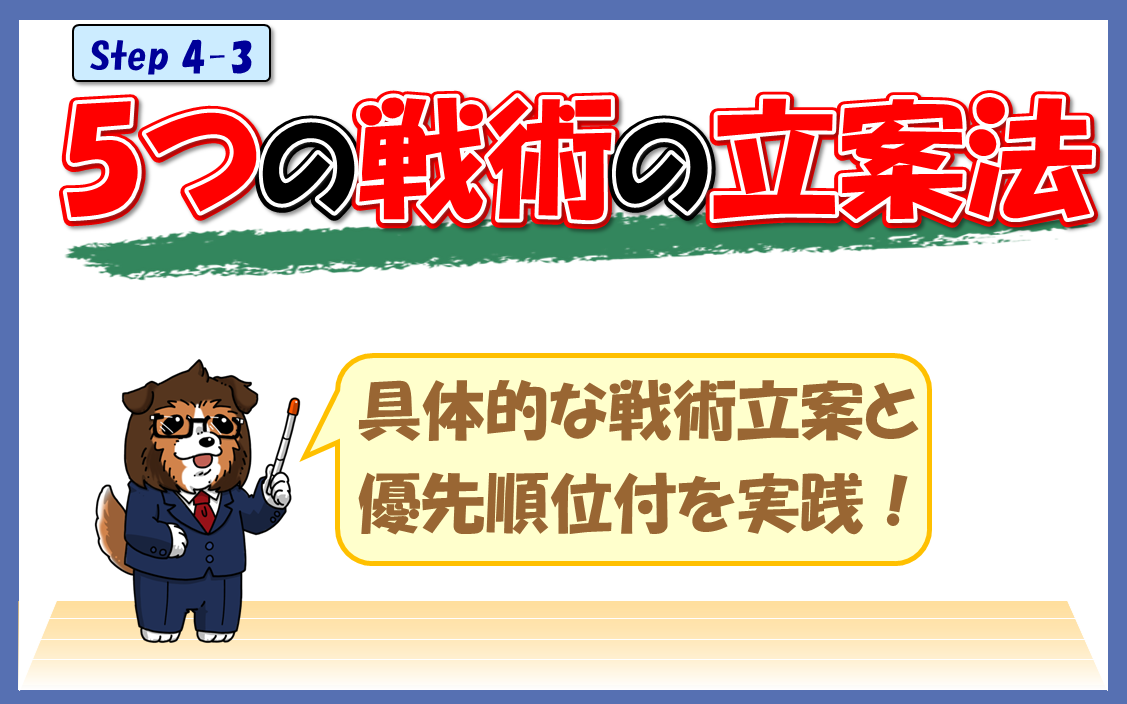

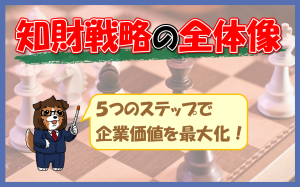
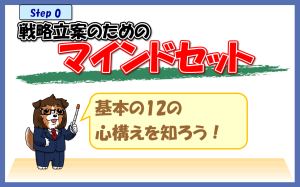
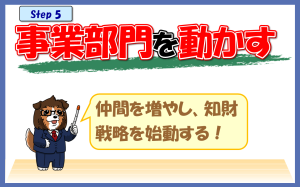
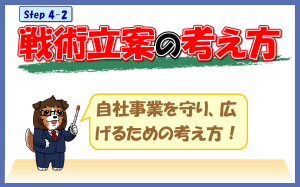
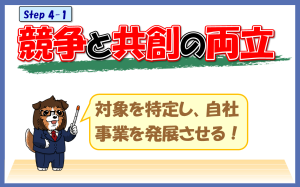
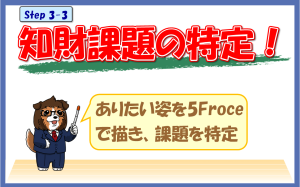
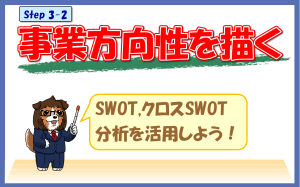
コメント