「先輩から『この特許、調べておいて』と特許番号を渡されたけど、どうすれば…?」
「気になる製品の特許情報、番号は分かっているんだけど、どこで検索するの?」
こんにちは!特許調査の沼へようこそ。
知財業務に携わり始めたばかりのあなた、特許文献の海を前に途方に暮れていませんか?
大丈夫です、一歩ずつ進んでいきましょう。
今回のテーマは、特許調査の基本中の基本「特許番号検索」です。
「特許番号から検索」する方法を知っていれば、特定の特許文献にピンポイントでたどり着けます。
これ、実はとっても便利で強力なスキルなんです。
この記事では、日本の特許情報を無料で調べられる「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を使って、誰でも簡単にできる「簡易検索」での特許番号検索方法を、具体的な手順とコツを交えて徹底解説します!
✓特許番号の種類とその意味がわかる。
✓ なぜ特許番号検索が便利なのか、そのメリットを理解できる。
✓ J-PlatPatの「簡易検索」で、迷わず特許番号検索を実行できるようになる。
✓ 特許番号検索のちょっとしたコツと注意点が身につく。
さあ、あなたも特許番号検索をマスターして、特許調査の第一歩を軽やかに踏み出しましょう。
そもそも「特許番号」って何? – 知っておきたい番号の種類
特許調査の話になると、必ず出てくる「特許番号」。
実はこれ、一つではありません。
主に使われる代表的な番号とその意味を簡単に押さえておきましょう。
- 出願番号(しゅつがんばんごう)
- 意味: 特許庁に特許を出願した際に、その出願一つひとつに付けられる受付番号のようなもの。
- 例 (日本): 「特願2024-123456」(「特願」+西暦年号ハイフン+6桁の連続番号)
- 使われる場面: 出願手続きの管理、特定の出願の審査状況を追跡する時など。
- 公開番号(こうかいばんごう)
- 意味: 原則として出願から1年6ヶ月が経過すると、その発明の内容が一般に公開されます。
この公開された特許出願公報に付けられる番号です。 - 例 (日本): 「特開2025-789012」(「特開」+西暦年号ハイフン+6桁の連続番号)
- 使われる場面: 最新技術の動向調査、他社の出願内容を確認する時など。
まだ特許として成立していなくても、どんな技術が出願されているかを知る手がかりになります。
- 意味: 原則として出願から1年6ヶ月が経過すると、その発明の内容が一般に公開されます。
- 特許番号(とっきょばんごう)
- 意味: 特許庁の審査をクリアし、晴れて特許として登録された権利に付けられる番号。
これが、いわゆる「パテントナンバー」です。 - 例 (日本): 「特許第7654321号」(「特許第」+7桁の連続番号)
- 使われる場面: 権利が成立している特許の確認、ライセンス交渉、侵害予防調査など。
- 意味: 特許庁の審査をクリアし、晴れて特許として登録された権利に付けられる番号。
これらの番号は、それぞれ役割が異なります。
調査の目的や、手元にある番号の種類を意識することが大切です。
なぜ「特許番号検索」が便利なの? – 3つの大きなメリット
「キーワードで検索すればいいのでは?」と思うかもしれません。
もちろんキーワード検索も重要ですが、特許番号検索には代えがたいメリットがあります。
- 確実性バツグン!ピンポイントで文献に到達
キーワード検索だと、言葉の選び方によっては関係ない文献がたくさんヒットしたり、逆に見つけたい文献が見つからなかったりすることも。
しかし、特許番号が分かっていれば、その番号に対応する文献に一発で、確実にたどり着けます。
迷子になる心配がありません。 - 競合他社の動向チェック(ウォッチング)に最適
気になる競合他社が取得した特許の番号や、公開された出願の番号をリストアップしておけば、定期的にその番号で検索することで、権利状況の変化(登録されたか、拒絶されたかなど)や、関連する新しい出願がないかを簡単にチェックできます。 - 調査時間を大幅に短縮!効率アップ
探したい特許が明確な場合、キーワードをあれこれ試行錯誤するよりも、番号で直接検索した方が圧倒的に早く目的の文献にアクセスできます。
忙しいあなたにとって、時間短縮は大きな味方ですよね。
J-PlatPatで挑戦!「特許番号から検索」する方法(簡易検索編)
お待たせしました。
ここからは、日本の特許情報を網羅した無料データベース「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)を使って、実際に特許番号検索を行う手順を解説します。
今回は、初心者でも使いやすい「簡易検索」機能を使ってみましょう。
ステップ1:J-PlatPatにアクセスし、「簡易検索」を選ぶ
まずは、J-PlatPatのトップページにアクセスします。
画面上部のメニューや、分かりやすい場所に「簡易検索」や「特許・実用新案」といった項目があるので、そこから進みます。
多くの場合は、トップページに直接キーワードや番号を入力できる検索窓があります。

ステップ2:「簡易検索」画面で番号を入力
「簡易検索」の画面、またはトップページの検索窓に、調べたい特許番号(出願番号、公開番号、特許番号など)を入力します。

入力時のポイント(日本の特許番号の場合):
- 出願番号:
「特願2024-123456」のように、「特願」やハイフンもそのまま入力してOKな場合が多いです。
あるいは、番号部分「2024-123456」だけでも検索できることがあります。 - 公開番号:
「特開2025-789012」と同様に、「特開」やハイフンを含めて入力します。 - 特許番号:
「特許第7654321号」の「特許」や「第」「号」は省略し、数字部分「7654321」のみで検索できるのが一般的です。 - 半角/全角:
基本的に半角で入力しましょう。 - 種別指定:
検索窓の近くに「番号種別」を選択するプルダウンメニュー(例:「出願番号」「公開番号」「特許番号」など)があれば、手元の番号の種類に合わせて選択すると、より確実に検索できます。
もしなければ、J-PlatPatが自動で判断してくれることもあります。
ステップ3:「検索」ボタンをクリック
番号を正しく入力したら、「検索」ボタンをクリックします。
ステップ4:検索結果を確認し、文献詳細へ
入力した番号に対応する特許文献が見つかれば、検索結果一覧に表示されます。
通常は1件だけヒットするはずです(同じ番号の文献は一つなので)。

文献名や番号の部分がリンクになっているので、そこをクリックすると、特許文献の詳細な内容(発明の名称、要約、特許請求の範囲、図面など)を閲覧できる画面に進みます。

いかがでしょう?
意外と簡単だったのではないでしょうか。
J-PlatPatの「簡易検索」は、特定の番号の文献をサッと確認したい時に非常に便利です。
ただし、より複雑な条件での検索や、大量の文献を効率的に絞り込みたい場合は、「詳細検索」機能などを使うことになりますが、それはまた別の機会にご紹介しま。
知っておくと便利!特許番号検索のコツと注意点
特許番号検索をスムーズに行うための、ちょっとしたコツと注意点です。
- 番号は正確に:
一文字でも間違えるとヒットしません。入力ミスがないか、よーく確認しましょう。
特に「0(ゼロ)」と「O(オー)」、「1(イチ)」と「l(エル)」などは間違いやすいので注意! - 番号の種類を意識する:
前述の通り、出願番号、公開番号、特許番号は別物です。どの種類の番号で検索しているのかを把握しておきましょう。 - ハイフンや記号の扱い:
J-PlatPatでは、日本の特許番号の場合、ハイフンや「特願」「特開」といったプレフィックスを付けても検索できることが多いですが、システムによっては数字のみで検索する必要がある場合も。
上手くいかない場合は、数字部分だけで試してみるのも手です。 - 外国特許の番号を検索する場合:
J-PlatPatでも一部の外国特許情報を検索できますが、国ごとに番号体系が大きく異なります。
国コード(例:US(米国)、EP(欧州特許庁)、CN(中国)など)を付けて検索する必要がある場合や、専用のデータベースを使った方が良い場合もあります。 - どうしても見つからない時は:
- まずは入力ミスを再度チェック。
- 番号の種類が正しいか確認。
- もし古い文献で、紙媒体から情報を得た場合、デジタル化の過程で稀に誤りがある可能性も(非常に稀ですが)。
- J-PlatPatの収録範囲外(例えば、非常に古い時代のものや、一部の特殊な文献)である可能性もゼロではありません。
【おまけ】特許番号って、どこで手に入るの?
「そもそも、検索するための特許番号はどこを見れば分かるの?」
という疑問も出てきますよね。
特許番号は、以下のような場所で見つかることがあります。
- 製品のパッケージや説明書:
ごく稀ですが、製品自体や説明書に特許番号が記載されていることがあります。(「特許取得済み 特許第〇〇〇号」のように) - 企業のウェブサイト:
知的財産に関するページや、技術紹介ページ、ニュースリリースなどで、自社技術の特許番号を公開している企業もあります。 - 学術論文や技術記事:
新しい技術を紹介する際に、関連する特許番号が引用されていることがあります。 - 競合他社の技術資料やIR情報:
他社の技術動向を調査する中で見つかることも。 - 他の特許文献から:
ある特許文献を読んでいると、その文献が引用している他の特許(引用文献)や、その文献を引用している後発の特許(被引用文献)の番号が記載されていることがあります。これを辿っていくのも有効な調査手法です。 - (もちろん)キーワード検索や分類検索の結果から:
これらの検索で見つけた重要な特許文献の番号は、控えておく習慣をつけると良いでしょう。
まとめ:特許番号検索をマスターして、特許調査の効率をグンと上げよう
今回は、特許調査の基本である「特許番号検索」、特に「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」の「簡易検索」機能を使った「特許番号から検索」する方法をご紹介しました。
特許番号さえ分かっていれば、狙った文献に一直線!このスキルは、あなたの特許調査を確実に、そして効率的に進めるための強力な武器になります。
最初は戸惑うかもしれませんが、この記事を参考に実際にJ-PlatPatで何度か検索してみれば、すぐに慣れるはずです。
さあ、今すぐアクション!
- 何か一つ、手元にある(あるいはインターネットで見つけた)特許番号を用意してみましょう。
- J-PlatPat(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)にアクセス!
- 「簡易検索」で、その番号を入力して検索してみてください。
特許番号検索ができるようになると、次はキーワード検索や特許分類を使った検索など、さらに高度な調査にもスムーズに入っていけます。
このブログでは、これからもあなたの特許調査スキルアップを応援する情報を発信していきますので、楽しみにお待ちください。
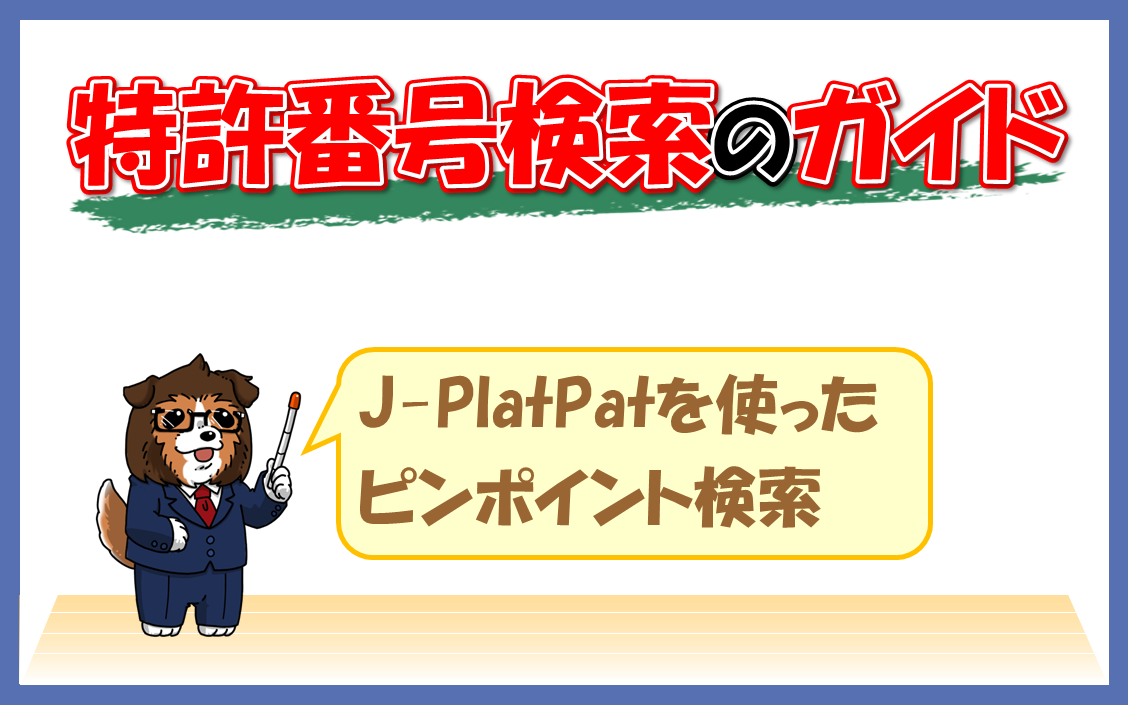


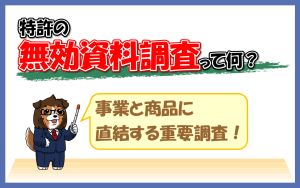
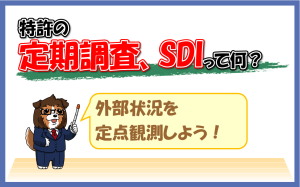
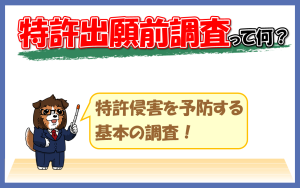
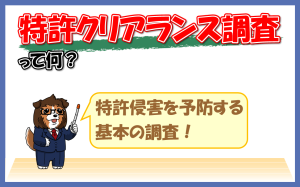
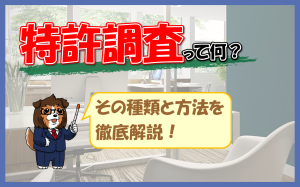
コメント