
特許の「定期調査」とか「SDI」とかいう言葉を聞いたことあるけど、
これって、具体的にどういったものなの?



それは、特許調査の一種で、どちらも定期的に
調査を行うという点で共通するものだね。



具体的にはどのような考え方で行うものなの?
そして、調査が終わったら、何をするの?



今回は、そのあたりについて詳しく解説していくよ。
特許調査、特に『定期調査』や『SDI』という言葉を聞いて、何から手をつければ…と不安に思っていませんか?
専門用語も多いし、調査範囲も広そうで、ちょっと圧倒されてしまいますよね。
でも、大丈夫です!
この記事では、そんなあなたの不安を解消するために、特許の「定期調査」と「SDI」の基本をお伝えします。
そして、実務で本当に役立つ効果的な活用法、そして調査結果をしっかり会社の力に変えるためのプロセスまで、初心者の方にも分かりやすく、ステップ・バイ・ステップで解説します。
この記事を読めば、自信を持って調査業務に取り組めるようになり、周囲の人からも一目置かれる存在になるはずです。
それでは、一緒に学んでいきましょう!
✓ 特許の「定期調査」、「SDI」とは何か。
✓ これらの調査をどのような方法で行うのか。
✓ 調査後は、どのような対応をする必要があるのか。
1.定期調査、SDI調査とは
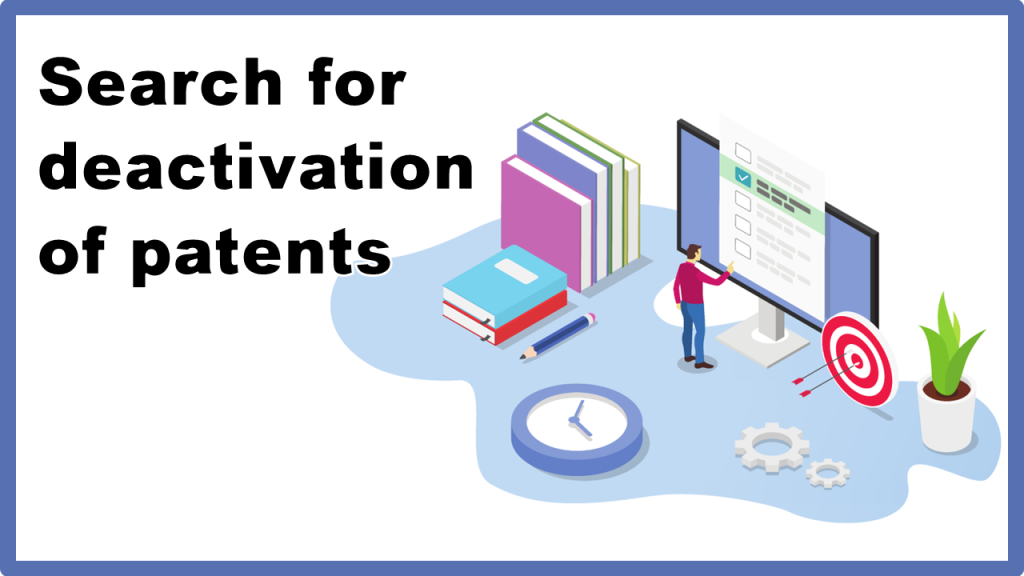
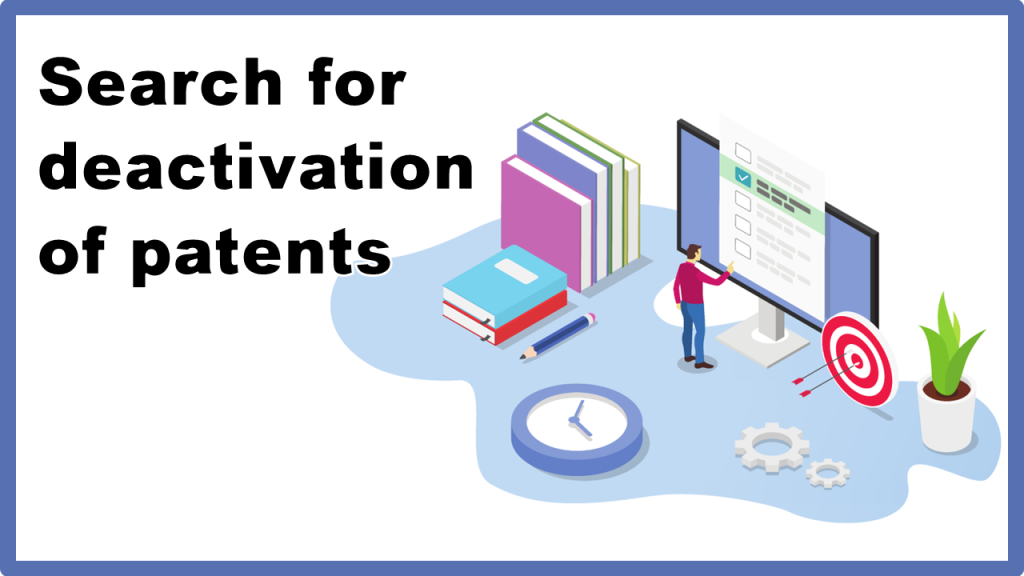
まずは基本の知識からです。
「定期調査」と「SDI」がそれぞれ何なのか、そしてなぜ重要なのかをしっかり押さえましょう。
「定期調査」とは? ~定期的に情報をチェックすること~
特許の定期調査とは、調査の範囲を決めて、定期的に特許の公開状況やステータス状況を確認することです。
つまり、新たに出願公開された特許の確認や、特定の出願の審査状況を確認することになります。
新しく公開された特許出願(公開公報)がないか、注目している特許出願の審査状況(登録されたか、拒絶されたかなど)に変化がないかなどを、継続的に確認していく活動です。
地道な作業に思えるかもしれませんが、これが会社の事業を守り、成長させるための大切な情報収集になります。
「SDI」とは? ~知りたい情報を自動でお届け!~
SDI調査とは、予め設定しておいた検索条件に合致する新しい特許情報が公開されると、自動的に通知してくれる仕組みのことです。
SDIとは、「Selective Dissemination of Information」の頭文字をとった略称です。
日本語で直訳すると、「情報の選択的発信」となります。
まさに、あなたが必要とする情報だけを選んで届けてくれる、便利な機能です。
SDIも定期調査の一種と言えます。
SDIのメリットは、次のようなことです。
・効率的:
毎回自分で検索しなくても、新しい情報だけを自動で受け取れること
・見逃し防止:
人手によるチェック漏れを防ぎ、重要な情報を見逃すリスクを減らせること
・網羅的:
設定した条件に基づいてシステムが検索するので、広範囲の情報を継続的にウォッチできること
SDIは、定期調査を効率的かつ効果的に行うための強力な味方と言えます。
なぜ定期調査・SDIが重要? ~会社の未来を守る情報収集~
特許における、定期調査やSDI調査を行う目的は何でしょうか?
その主な目的と、それを怠った場合のリスクを見てみましょう。
技術動向の把握:
特定分野の最新技術動向がどのようになっているかを把握することを目的とします。
これを知らないと、自社の研究開発が時代遅れになったり、世の中のニーズとズレてしまったりする可能性があります。
「車輪の再発明」のような無駄な開発投資を防ぐ意味でも重要です。
事業、商品のクリアランス(侵害予防):
これから始めようとする事業や、新しく販売しようとする商品が、他社の特許権を侵害しないか、最新の状況を把握することを目的とします。
もし他社の有効な特許権を知らずに侵害してしまうと、最悪の場合、製品の販売停止や多額の損害賠償を請求されるリスクがあります。
これは会社の存続にも関わる重大な問題です。
定期的なチェックで、このリスクを最小限に抑える必要があります。
競合他社動向の把握:
ライバル企業がどのような技術分野に力を入れて出願しているか、その動向から彼らが今後どのような事業展開を考えているかを推測することを目的とします。
競合の動きをいち早く察知することで、自社の研究開発戦略や事業戦略に活かし、競争で優位に立つためのヒントを得ることができます。
「気づいた時には市場を取られていた…」といった事態を防ぐためにも、競合の動きは常に把握しておきたいものです。
このように、定期調査やSDIは、会社の事業を守り、未来の成長戦略を描く上で、欠かせない情報収集活動なのです。
2.効果的な調査の方法


重要性がわかったところで、実際に調査を進めるための準備に入りましょう。
ここでの準備が、調査の質を大きく左右します。
2-1.何を調べる?~調査の「観点」を決めよう~
まず、「どのような観点で」調査を行うかを明確にすることが重要です。
闇雲に調べるのではなく、目的意識を持つことが大切です。
観点の例としては、以下のようなものがあります。
・事業内容:
自社が行っている、またはこれから行う予定の事業に関連する技術。
・プロジェクト内容:
現在進行中の特定の研究開発プロジェクトに関連する技術。
・商品コンセプト:
新しく開発中の商品の核となる技術やアイデア。
・研究テーマ:
基礎研究など、特定の技術テーマ。
【具体例】
例えば、あなたの会社が「AIを活用した自動運転技術」に関するプロジェクトを進めているなら、以下のような観点が考えられます。
- 「特定のセンサー技術(例:LiDAR、ミリ波レーダー)に関する最新の特許」
- 「画像認識アルゴリズムに関する他社の出願動向」
- 「自動運転の制御システムに関する競合他社の特許」
2-2.どれを調べる?~調査対象の「選定」基準~
上記の観点があるとはいえ、会社の中には、様々な事業やプロジェクトがあります。
すべてについて詳細な定期調査を行うのは現実的ではありません。
そこで、どのテーマを優先的に調査するか、「選定」する必要があります。
判断に迷ったときは、以下の視点を参考にしてみてください。
それぞれ考え方は色々とあるかと思いますが、参考として以下のような視点を持ってみてはいかがでしょうか。
社内における重点課題か:
会社の経営計画や研究開発ロードマップ上で、重要度が高いと位置付けられているテーマか
競合他社の多い領域か:
多くのライバル企業がひしめき合い、技術開発が活発な分野か(競合が多いほど、動向把握の重要性は増します) 売上等の金額的インパクトが大きいか:
その技術が関連する製品や事業の売上規模が大きいか(侵害リスクの影響が大きい分野は優先度が高い)
社内情報を収集しつつ、このような視点を入れてみてはいかがでしょうか。
2-3.どうやって探す?~効果的な「検索式」作成のコツと注意点
検索式の作成方法は、一般的な調査と大きく変わりはありません。
キーワード、出願人・権利者(競合)、FI・IPC・Fターム等の特許分類、等を用いると良いでしょう。
検索式の具体的な作成方法は、こちらの記事も参考にしてみてください。
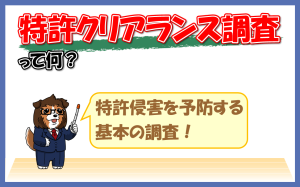
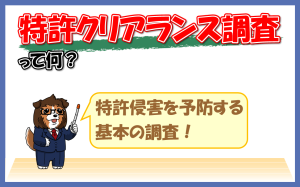
2-4.いつ調べる?~目的に合った調査「タイミング」~
SDIで情報を受け取るタイミング(頻度)も重要です。
目的によって適切なタイミングは異なります。
・逐次(情報更新の都度、または毎日):
侵害予防(クリアランス)調査など、一刻も早く情報をキャッチしたい場合。
他社の権利化動向をリアルタイムで把握したい場合。
・週次(週に1回):
競合他社の出願動向や、特定の特許出願の審査状況(ステータス)を把握したい場合。
(特許庁の審査情報は週単位で更新されることが多いです)
・月次(月に1回):
特定技術分野の幅広い技術動向を、ある程度まとまった情報量で把握したい場合。
すぐにアクションが必要ではないが、定期的に状況を知っておきたい場合。
どのタイミングが良いか迷ったら、調査の目的と、どれくらいの速報性が求められるかを考えてみましょう。
2-5.何を使って調べる?~調査「ツール」の選び方と活用Tips~
SDI調査を行うには、専用のツールを使うのが一般的です。
無料ツール:
J-PlatPat(特許情報プラットフォーム): 特許庁が提供する無料のデータベースです。
基本的なキーワード検索や分類検索、そしてSDI機能(マイリストのウォッチ機能など)も利用できます。
まずはここから試してみるのがおすすめです。
メリット:
無料ツールであることです。
日本の特許情報はほぼ網羅しています。
デメリット:
海外特許の検索機能は限定的です。
高度な分析機能や共有機能はあまりありません。
SDIの設定が少し分かりにくいかもしれません。
有料ツール(商用データベース):
様々な企業から提供されており、それぞれ特徴があります。
(例:JP-NET、Shareresearch、Patentfield、Derwent Innovationなど ※具体的なツール名は会社で導入しているものなどを確認してください)
メリット:
高度な検索・分析機能、海外特許情報へのアクセス、複数人での情報共有機能、使いやすいインターフェース、充実したサポート体制など、効率的に調査を進めるための機能が豊富です。
SDI設定も簡単に行えるものが多いです。
デメリット:
利用料金がかかります。
ツール選びのポイント:
必要な機能は何か:
海外特許も調べるか?高度な分析(パテントマップ作成など)が必要か。チームで情報を共有したいか。
予算は:
無料で十分か、有料ツールを導入する価値があるか。
操作性・サポート:
初心者でも使いやすいか。困ったときにサポートは受けられるか。
会社で既に導入しているツールがあれば、まずはその使い方をマスターしましょう。
SDI設定・運用のTips:
アラート設定を工夫しよう:
メールの件名に調査テーマ名を入れるなど、何の通知か一目で分かるようにすると便利です。
3.調査結果を活かす!~調査後の対応プロセス~


さて、SDIで情報が届くようになりました。
でも、ここで終わりではありません。
むしろ、ここからが重要です。
届いた情報をしっかり吟味し、会社の活動に活かしてこそ、調査の意味があります。
「調査しっぱなし」を防ぎ、結果を「行動」に繋げるためのステップを見ていきましょう。
調査後の対応として、
・選別(スクリーニング)
・評価
・通知
といった対応が必要です。
情報を選び出す「選別(スクリーニング)」のコツ
SDIで届く情報には、本当に重要な情報もあれば、あまり関係のない情報(ノイズ)も含まれています。
まずは、この中から「これは注目すべき!」という情報を選び出す作業、「選別(スクリーニング)」が必要です。
効率的なスクリーニングのコツ:
<まずはココを見る>
全文を読む前に、
・「発明の名称(タイトル)」
・「要約」
・「筆頭クレーム(特許請求の範囲の一番最初の項目)」
をチェックしましょう。
これらを見るだけでも、大まかな内容と重要度が判断できることが多いです。
<優先順位をつける>
全ての情報を同じようにじっくり見るのは大変です。
自社の事業や開発テーマに関連度が高そうなもの、権利範囲が広そうなものなどを優先的にチェックしましょう。
<基準を決める>
複数人で分担する場合や、継続的に行う場合は、「どのような基準で要注目/不要を判断するか」を明確にしておくと、判断のブレが少なくなります。
価値を見極める「評価」のポイント
スクリーニングで選び出した「要注目」の特許情報について、さらに深く読み込み、「自社にとってどのような意味を持つのか」「どのような対応が必要か」を「評価」します。
どんな観点で評価する?:
・自社製品/技術との関連性:
自社の製品や開発中の技術と、どの程度関連があるか?
(特に、侵害リスクがないか?逆に、利用できる技術はないか?)
・技術的な新規性・進歩性:
その特許技術は、どれくらい新しいのか?画期的なのか?
・競合の脅威度:
これが権利化されると、自社の事業にどれくらい影響があるか?
・権利状況:
現在どのような状態か?
(出願中? 登録済み? 拒絶された? 権利期間はいつまで?)
・権利範囲の広さ:
クレーム(特許請求の範囲)は、広い範囲をカバーしているか?それとも限定的か?
評価シート項目例:
評価結果を記録に残しておくと、後で役立ちます。
簡単なものでも良いので、以下のような項目を含めて記録する習慣をつけると良いでしょう。
・書誌事項(公報番号、発明の名称、出願人など)
・簡単な技術概要
・自社との関連性(該当製品/技術、侵害リスク評価など)
・注目ポイント
・対応案(詳細調査要否、設計変更検討、情報共有など)
・評価日、評価者
(応用編)パテントマップでの分析:
たくさんの情報を評価する場合、個々の文献だけでなく、全体像を可視化する「パテントマップ」という手法も有効です。
どの技術分野に出願が集中しているか、どの企業が活発かなどをグラフなどで表現します。
これは少し応用的なテクニックですが、知っておくと分析の幅が広がります。
パテントマップに関しては、こちらの記事も参考にしてみてください。


関係者に伝える「通知」と連携
評価した結果、「これは重要」「対応が必要」と判断した情報は、関係者に速やかに「通知」し、「連携」して対策を検討する必要があります。
これが最終的なアウトプットです。
誰に、何を、どう伝える?:
・誰に:
その情報に最も関係の深い部署や担当者
(例:研究開発部門の担当者、法務・知財部の上司、事業部長など)
・何を:
評価結果(特に注目すべき点、自社への影響、考えられる対応案など)を分かりやすくまとめて。
・どうやって:
報告書を作成する、メールで要点を伝える、会議で説明するなど、内容の重要度や緊急度に応じて適切な方法を選びます。
上司・先輩・関係部署との連携が重要:
・抱え込まない:
自分だけで判断せず、評価結果や対応案について、必ず上司や先輩に相談しましょう。
特に侵害リスクに関わるような重要な情報は、速やかに報告することが鉄則です。
・関係部署を巻き込む:
技術的な内容は研究開発部門、法的な判断は法務部門など、専門的な知見を持つ部署と連携することが不可欠です。
積極的にコミュニケーションを取りましょう。
・分かりやすく伝える努力:
専門外の人にも理解できるよう、専門用語を使いすぎず、結論から先に話すなど、伝え方を工夫しましょう。
・報告後のフォローアップも忘れずに:
報告して終わりではなく、提案した対策がきちんと検討・実行されているか、必要に応じてフォローアップすることも大切です。
4.まとめ
今回は、特許の定期調査と効果的なSDI活用法について、特に知財部に配属されたばかりの皆さんに向けて、基本から実践的なコツまで解説してきました。
今回のポイントおさらい
・定期調査・SDIは、技術動向把握、侵害予防、競合監視のために非常に重要
・調査は目的と観点を明確にしてからスタート
・SDIの効果は検索式の質で決まる!キーワード、分類、演算子を使いこなし、定期的な見直しを忘れずに
・調査タイミングやツールは目的に合わせて選ぶ
・調査結果は「選別→評価→通知・連携」のプロセスでしっかり活かす
・上司・先輩・関係部署との連携が成功のカギ
この記事が、あなたの知財パーソンとしての第一歩を、少しでも後押しできれば嬉しいです。
【次の一歩へ】
調査全般のことについて、より広く知りたい方はこちらの記事も参考にしてみてください。
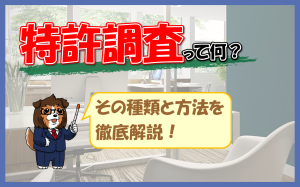
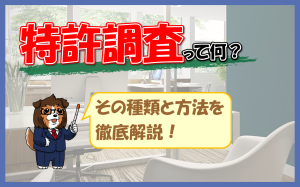
今日という日が、あなたにとって素晴らしい学びの一日となりますように!
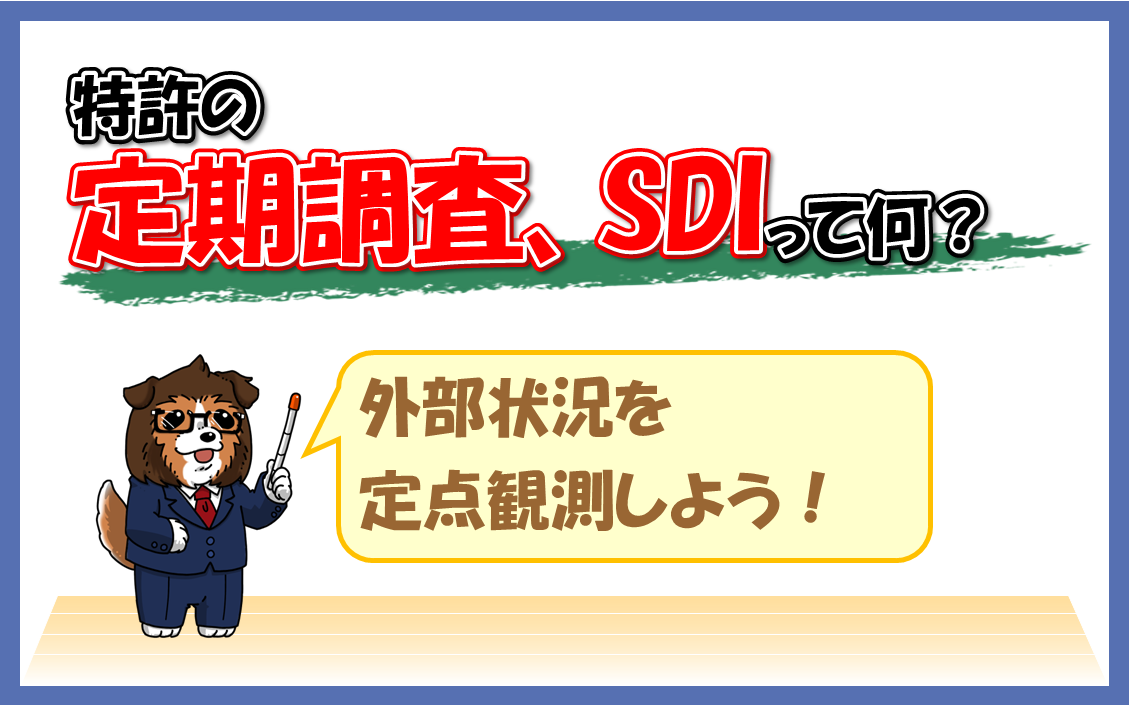

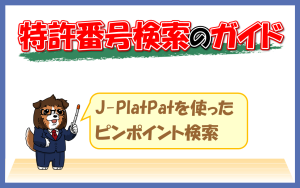
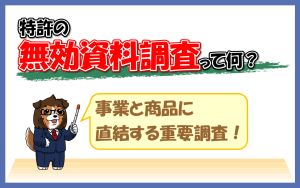
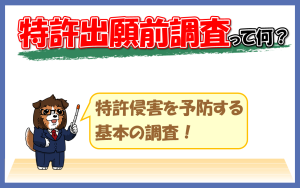
コメント